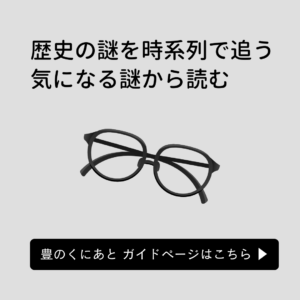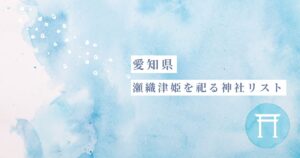お寺や神社を歩いていると、「八大龍王」という名前に出会うことがあります。ときには石像があったり、祠の名前になっていたり。
でも、初めて聞いた方にとっては「龍?八体?どういう意味だろう」と思うかもしれません。
雨や水をつかさどる、龍の王たち
「八大龍王」は、仏教に登場する「八体の龍神」たちのことを言います。
それぞれに名前があり、本来はインドの神話や仏典の中に登場する存在です。
もともと龍は、インドや中国、日本でも「水の神」「雨を呼ぶ神」とされてきました。
田畑を潤す恵みの雨をもたらす一方で、洪水などの災害ともつながる、自然の強大な力の象徴です。
そんな龍たちの中でも、とくに信仰されたのが「八大龍王」。
お経の世界では、仏さまの教えを守る存在として、海や湖、川のほとりなどに祀られてきました。
日本ではどんな風に祀られてきたの?
日本に仏教が伝わったあと、八大龍王は次第に「雨乞い」や「水神さま」として信仰されるようになります。
とくに修験道(しゅげんどう)や山岳信仰の中では、山にこもる僧たちが祈りをささげ、水の恵みを願いました。
そういえば、かつて登った大分県中津市山国町の中摩殿畑山の山頂には八大龍王が祀られていました。
あの山は英彦山への遥拝所でした。

なぜ「八」なの?
実際には、龍神さまはたくさんいます。でも「八」という数字には、日本でも中国でも「豊かさ」「繁栄」といった意味があります。
「八百万(やおよろず)の神」と同じように、「たくさん」「すべて」といった意味をもつ特別な数字なんですね。
お寺によっては八王をそのままに表すのではなく、一王の姿をとって仏像をお祀りするところもあるようです。
こんな場所で出会えるかも
- 山あいの滝のそば
- 祠(ほこら)に「八大龍王社」と刻まれている
- 石碑に「八大龍王護持」などの文字
- 神仏習合の名残がある地域
- 山頂?
この記事を読んでいる方におすすめの記事
八大龍王は天照大神の荒魂「瀬織津姫」と関連があるのか?↓

中摩殿畑山を登った時の記事↓