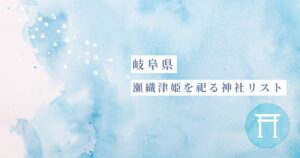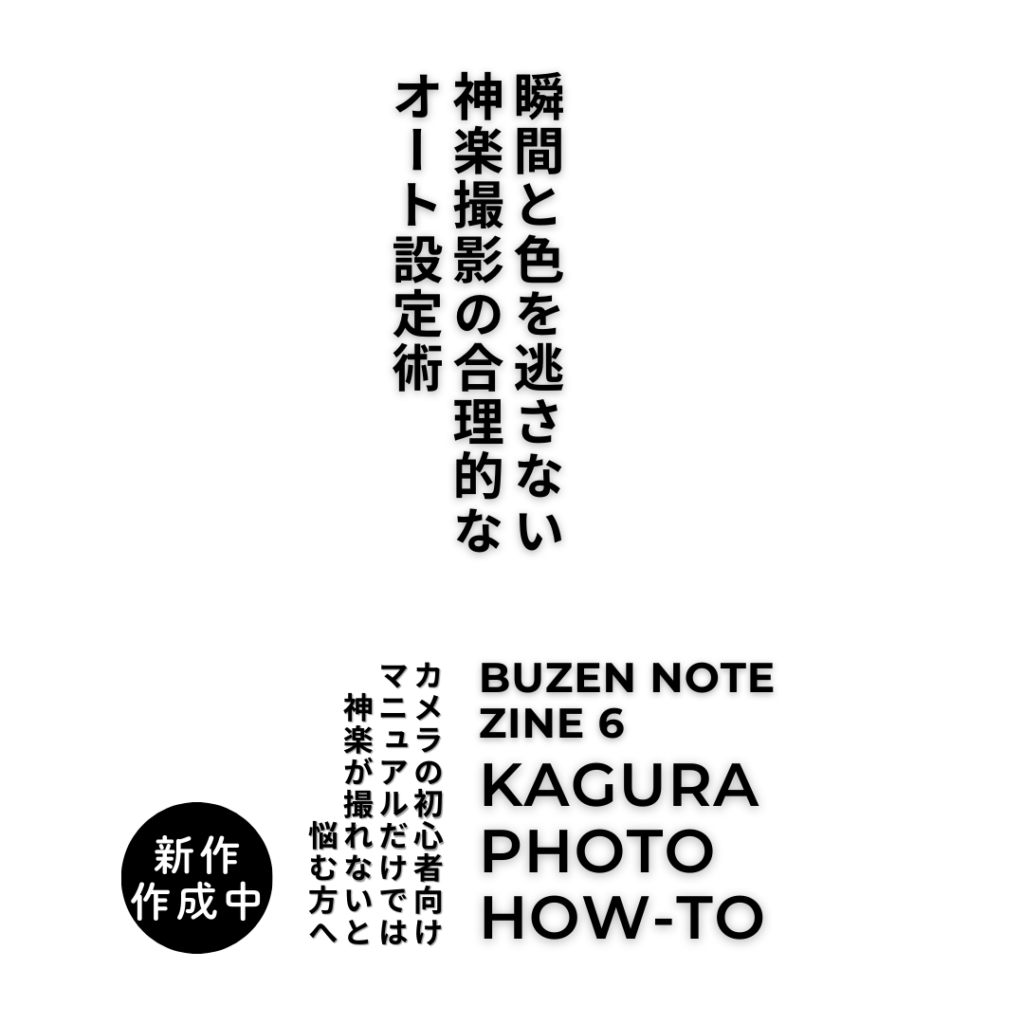宇佐神宮や六郷満山の歴史書を読み進めるうちに、あらためて自覚したことがあります。
自分が本当に知りたいのは、その文献に書かれる以前の歴史だ、と。
それは、史書には記録されず、神社の御祭神からもその名を消された、一対の男神と女神の存在。
この仮説を頭に置いて、豊前やその周辺地域を巡る旅を続けていると、不思議と「やはり何かある?」と思わせる痕跡が、次々と目に飛び込んでくるのです。
石灯籠がもう一つの歴史を語る?



その歴史の跡の一つが、春日灯籠と四角錐の笠をした石燈籠の存在でした。
愛媛県の日尾八幡神社では、この二種類の石燈籠が並んでいました。
竿と呼ばれる土台の上の部分が円柱のものと、四角形のもの。
円柱のものは、庭園でも見られる「春日灯篭」と呼ばれる石灯籠です。
春日灯籠はその美しさから、神社仏閣だけでなく、現在では庭園にもよく置かれるそうです。
「新しいものだけならともかく、一部古い燈籠もある。元々ここには春日灯篭がずっとあったのだろうか。それにあ合わせて新しい燈籠も春日灯籠で揃えられたのか?」
その疑問を抱えたまま、 Amazonでようやく見つけた専門書は、昭和40年代の「石燈籠新入門」。
そこには「祓戸型」と書かれていましたが、「祓」が水の女神を指すのかは書かれていませんでした。
しかし、本には「石灯籠は奈良時代に仏教と共に日本へ渡ったこと」「燭台としての役割のほか、神仏に供養として献ずるもの、つまり供物の一種」とありました。
また、本には石燈籠は一流の石工によって作られたものであることも伝えられていました。
石燈籠の形には、何か意味があるのだろうか。
最初、石灯籠といえば、図鑑に数多く載っていた、特徴ある円柱の竿をした「春日燈籠」しか目につきませんでしたが、各地を巡るうちに、屋根が四角錐をした石燈籠をよく目にしていることに気づきます。
図鑑にはほとんど情報がなかったのですが、「四角型石燈籠」のうち「神明形」と書かれていました。
「神明」とは、天照大神が祀られる神社の名前です。
以前私が春日燈籠の存在に気づいたみやこ町のある神社でも、同じような笠が四角錐の石燈籠があったのです。
その四角錐の笠をした石灯籠は、各地に残る「金毘羅燈籠」と同じ形でもありました。
もし四角錐の石燈籠が金毘羅様への献花であるなら、このサイトで立てている仮説、牛頭天王(スサノオ)=饒速日命=金毘羅様と一致します。
また、四角錐の石灯籠と春日灯篭が一対であれば、かつての信仰(男神と女神)を示す可能性があります。
あくまで、目で見たものからの仮説ですし、石灯籠の情報も大変少ないので現時点では何ともいえません。
しかしデータの数が増えたら、また何か法則が見つかるかもしれません。
「消えない痕跡」を追いかける理由
歴史の記録は、明治時代に神楽のセリフが変えられた歴史からも分かるように、時の権力によって書き換えられることがあります。
それはある神社の宮司さんや、神楽の舞手からも教わりました。
しかし、文字で紙に書かれたものは変えられても、石灯籠のように簡単に壊せないものや、汐汲み神事のように何百年も続いてきた祭り、神社の位置、古墳といった、有形・無形の「痕跡」は、当時の事実を静かに語り続けているように感じます。
文献にはない、もう一つの歴史が、この国には今も息づいているのではないでしょうか。
過疎化が進む地方を巡るうち、このままでは、せっかく残された貴重な歴史の跡が、そう遠くない未来に消えてしまうかもしれない。
そう思うと、この「謎」を追わずにはいられません。
私の活動は決して「何が正しいか」を証明するものではありません。
ただ、目の前にある「事実」から、失われた歴史のストーリーを、可能性のレベルでもいいから、書き残すこと。
今の時代、「徐福」「天照=男神」という仮説を口にするだけでもう非科学的と一笑に付される雰囲気はあります。
が、北部九州エリアを歩いているうちに「本当に違うのだろうか?」と思う歴史の跡が目に付くのです。
素朴な疑問を個人的に調べ続けているだけですが、それを見て、何か感じる方も出てくるかもしれない。
そしてその疑問に答えてくれる人も出てくるかもしれない。
そんな気持ちで旅を続けています。
この記事を読んでいる方におすすめの記事
陰陽一対の御祭神の謎とは?↓

滝の神「瀬織津姫」と牛頭天王のつながりはなぜ消されたのか?↓
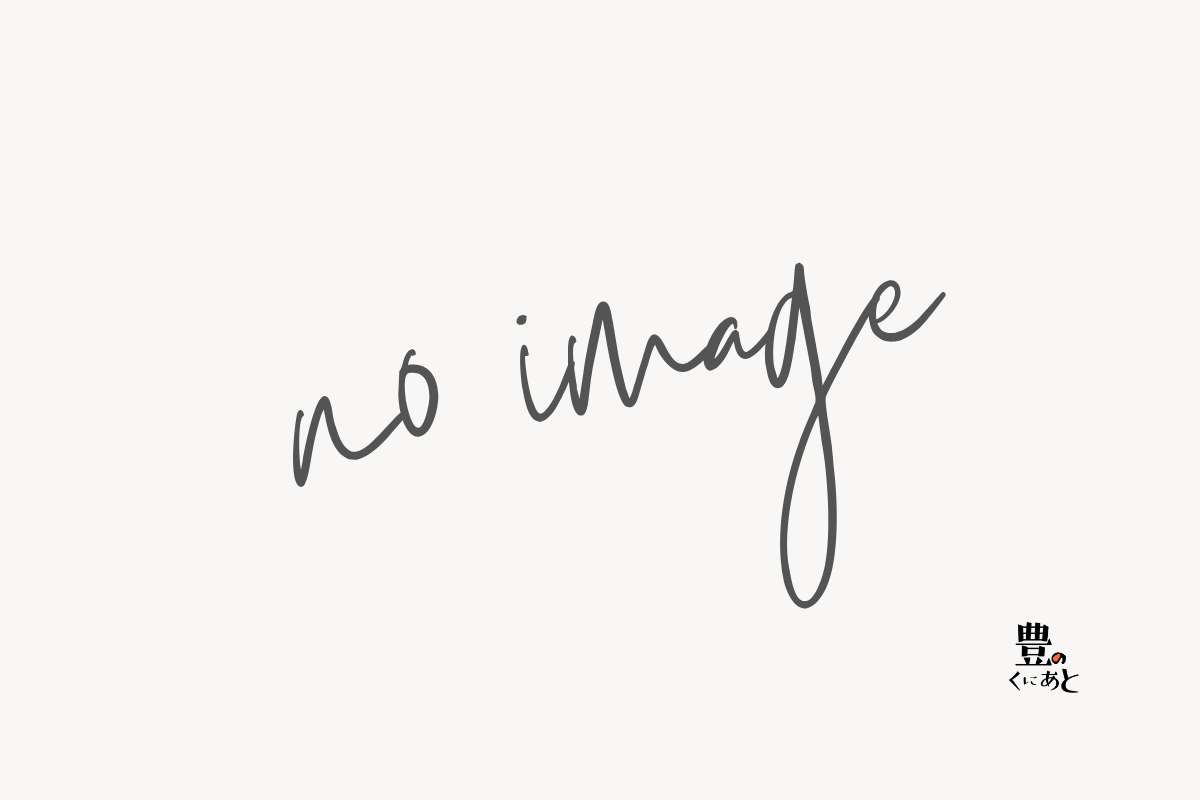
歴史の謎をまとめて読みたい方はこちらから↓




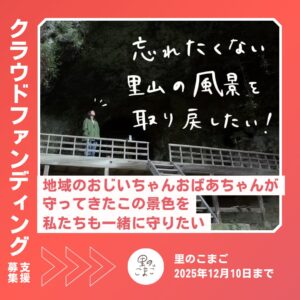


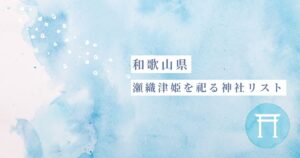
![[富士フイルム フジノンレンズ XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR]で神楽を撮る | 撮影方法と神楽の作例集 (祭りスナップの作例も)](https://toyonokuniato.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG_1608-300x225.jpg)