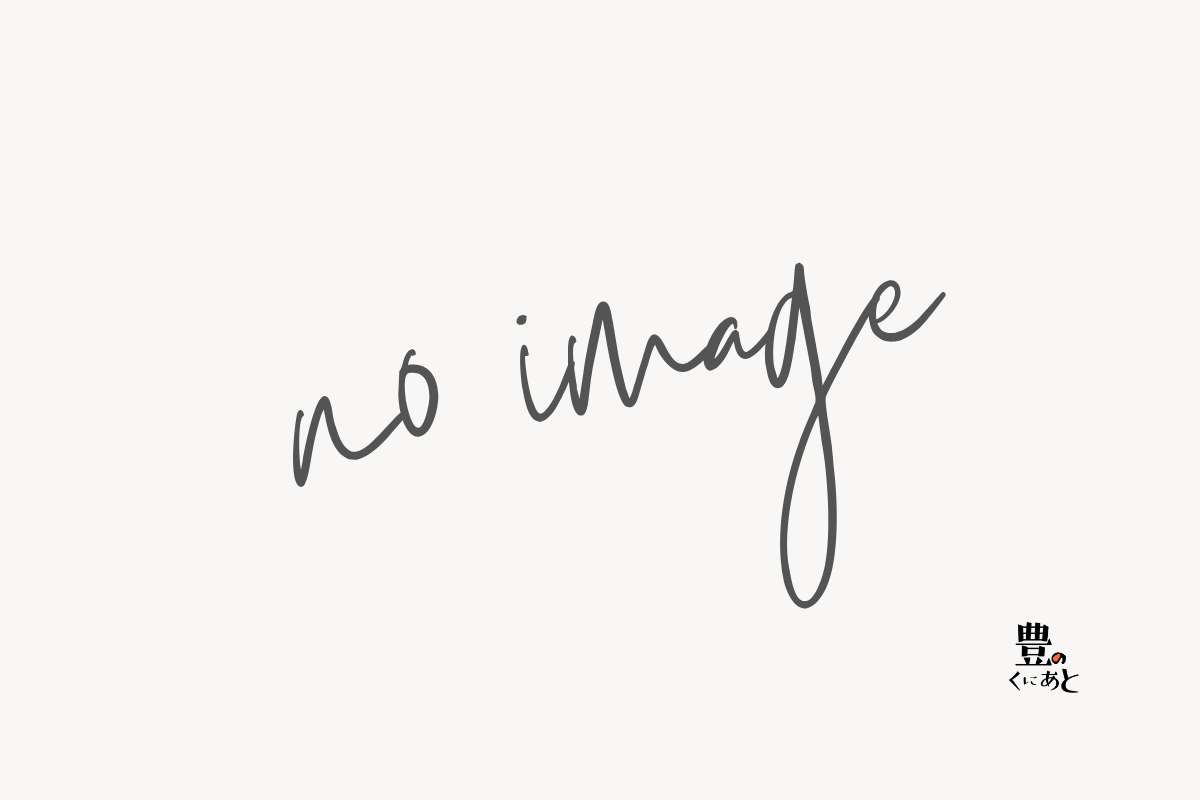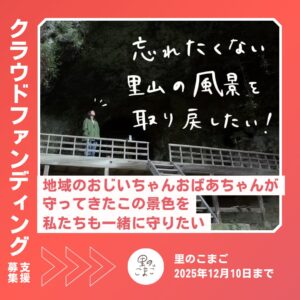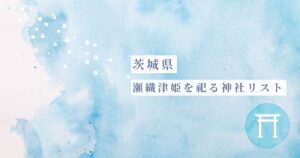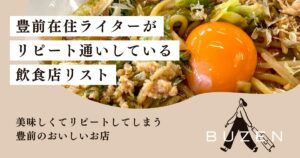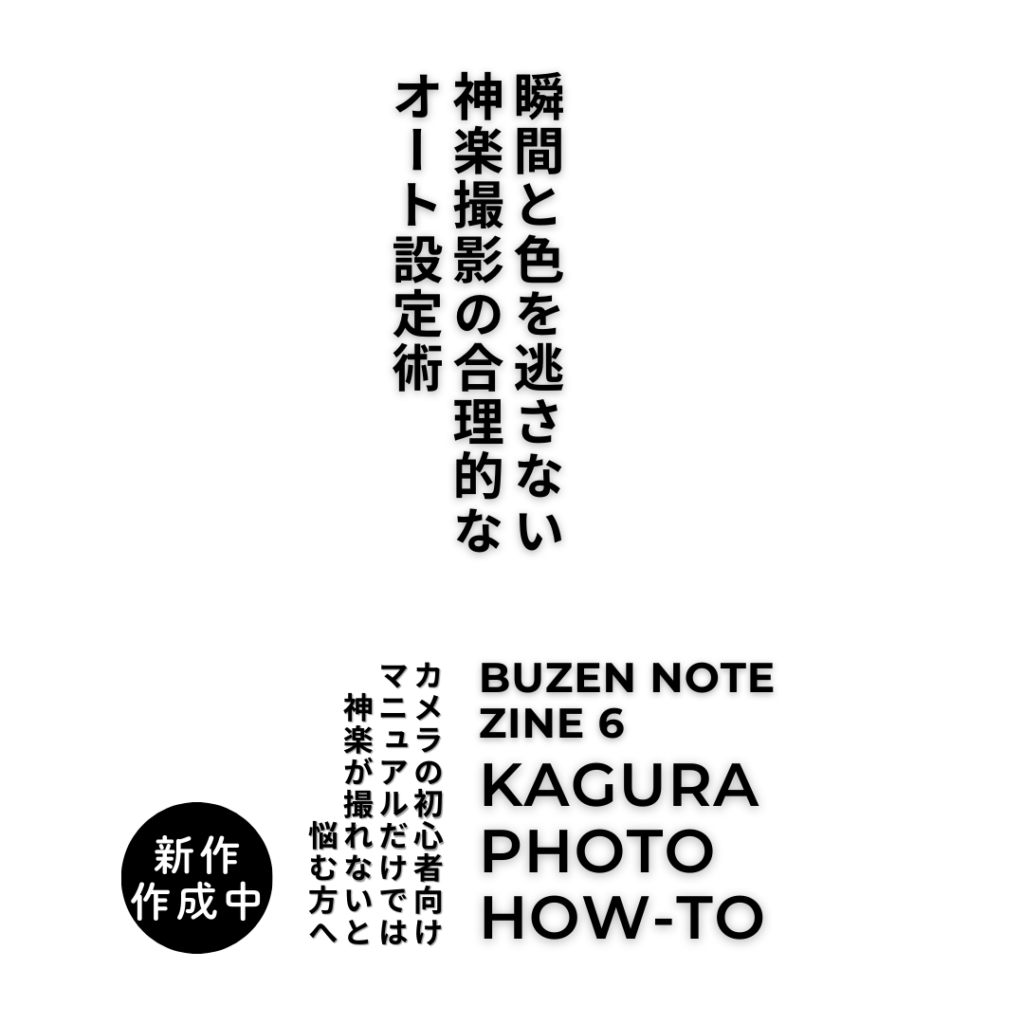日本の各地には、恐ろしい姿をしながらも、実は五穀豊穣や無病息災を祈る「鬼」の祭りが伝わっています。
中でも、姫路と国東半島に残る「鬼会(おにえ)」と呼ばれる祭礼には、奇妙な共通点があります。
今回は、姫路と国東半島の「鬼会」の共通性を手がかりに、火を扱う鬼と、「荒神(こうじん)」と呼ばれる神のつながりを、個人的な見解で考察していきます。
姫路と国東半島:遠く離れた地で「鬼会」が似ている理由
姫路にある廣峯神社(ひろみねじんじゃ)と、国東半島に伝わる「鬼会」。
廣峯神社の公式サイトによると、かつて正月14日に行われていた「鬼会」は、「天地斉整(てんちせいせい)」の祭りとして信仰を集め、赤鬼と青鬼が松明や矛を持って舞う行事だったそうです。
そして、この「鬼会」は「疫神祭(えきじんさい)」とも書かれ、現在の節分祭に受け継がれているといいます。
さらに姫路市には、八徳山八葉寺(はっとくさん はちようじ)に「修正会鬼会式(しゅしょうえおにえしき)(鬼追い)」が伝わっています。
一方、大分県の国東半島、特に天念寺(てんねんじ)で旧暦の1月7日に行われる「修正鬼会(しゅじょうおにえ)」は、国の重要無形民俗文化財にも選定されています。
五穀豊穣や無病息災を祈願する火祭りであり、登場する鬼は仏の化身とされ、赤鬼と黒鬼(ただし見た目には「青」鬼)が松明を振り回します。
これらの「鬼会」には、いくつかの共通点が見えてきます。
- 疫病や災厄の鎮静(廣峯神社の「疫神祭」)
- 五穀豊穣や無病息災の祈願
- 赤鬼が登場し、松明を振り回す「火祭り」としての要素
- 寺院(八葉寺や天念寺など)が関わる行事
遠く離れた地域で、これほど似た祭りが伝承されてきたのは、単なる偶然なのでしょうか?
牛頭天王と「鬼」の習合:疫病を鎮める神の姿
私が追ってきた牛頭天王というキーワードは、この「鬼会」にも繋がってきます。
牛頭天王は、古くから疫病を鎮める神として日本中に広まりました。
京都の祇園祭も、そのルーツは疫病鎮静にあるとされています。
牛頭天王は、インドの祇園精舎の守護神とされながらも、日本ではスサノオノミコトと習合してきました。
そして、牛頭天王が疫病神を追い払う際に、「鬼」の姿で現れるという信仰も生まれました。
疫病という目に見えない恐怖を具現化し、それを打ち払う象徴として「鬼」が用いられたのかとイメージしました。
愛媛県宇和島市の夏祭り「うわじま牛鬼まつり」でも、祭りのシンボル「牛鬼」が市内中心部を練り歩きます。
四国でも「牛」と「鬼」の組み合わせが見られます。
廣峯神社の「鬼会」が「疫神祭」とも書かれるのは、牛が関わる信仰(牛頭天王?)と結びつているからではと、私はつい想像してしまうのですが、どうなのでしょう。
「荒神」の面が語る古代の記憶
さらに、豊後高田市夷(えびす)に残る約200年前の「荒神(こうじん)」の面も気になっています。
「荒神」は、地域によって様々な性格を持つようですが、竈(かまど)や屋敷を守る神として、また時には荒々しい力を持つ神として信仰されてきました。
「豊前神楽の範囲が豊後高田市に及ぶ」と教えてくれた郷土史家の言葉は、この地域の信仰が広範囲で共有されていたことを示唆しています。
夷里神楽(えびすざとかぐら)の「荒神」の面は、国東半島の「鬼会」に登場する鬼、そしてもしかしたら牛頭天王信仰と何らかの繋がりを持っているのかもしれないと思う共通点でした。
さらに深堀り
これまで探してきた「右三つ巴紋」や「瀬織津姫」に関する記事も、今回のテーマと深く関連しています。
ぜひ併せてご覧ください。
右三つ巴紋と左三つ巴紋の違いとは?↓

天照大神の荒魂「瀬織津姫」の謎↓

古代史の謎の記事をまとめて読む↓