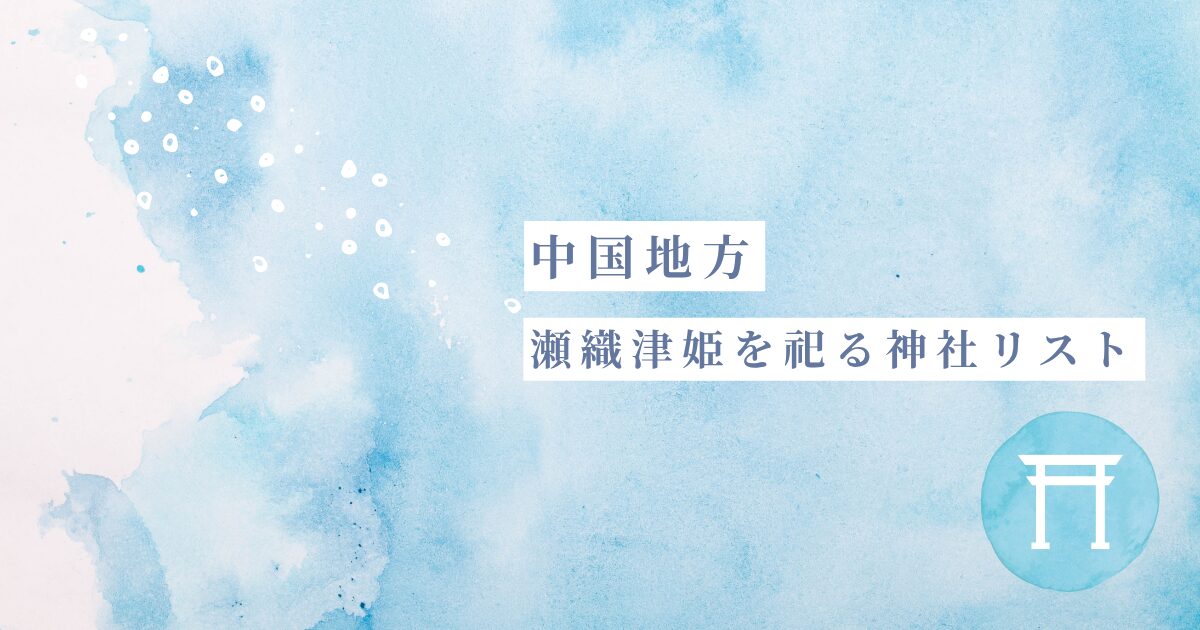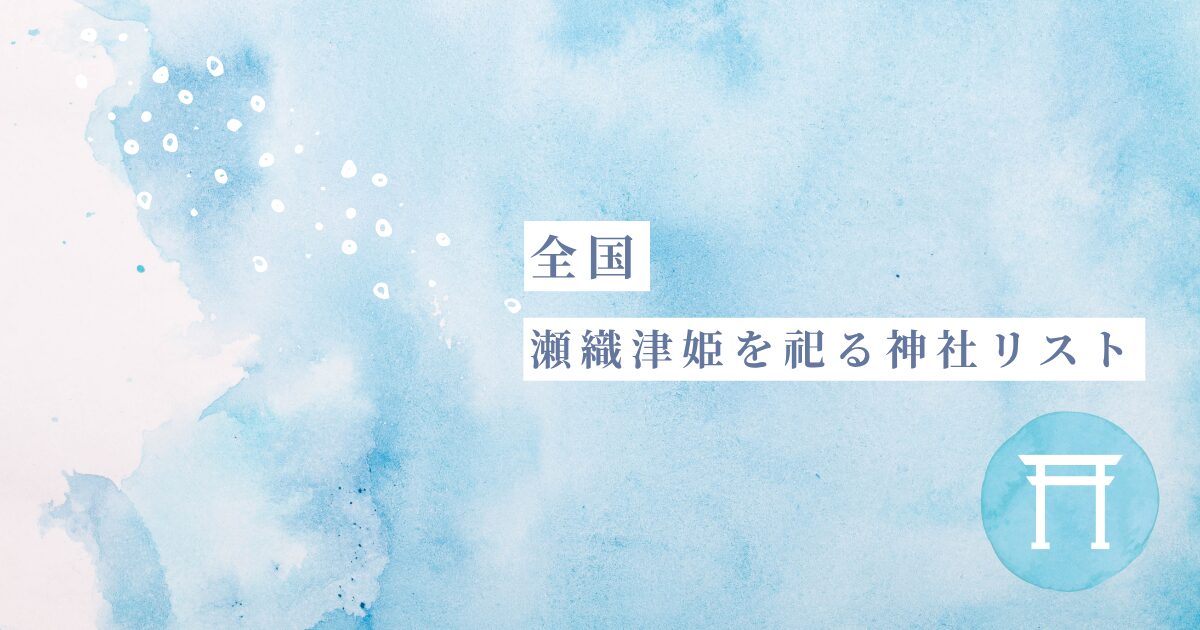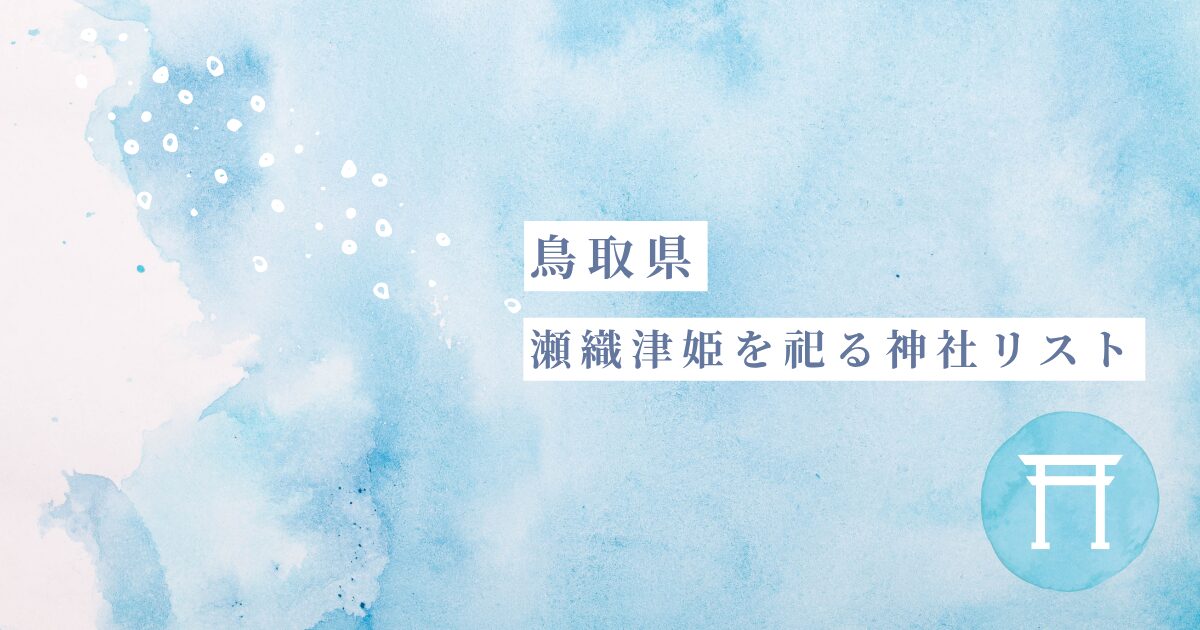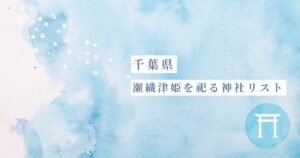古来より、日本各地には数多の神々が祀られてきました。
しかし、その中には、歴史の表舞台から姿を消し、ひっそりと隠された存在として語り継がれてきた神様もいます。その代表格こそが、瀬織津姫(せおりつひめ)。
瀬織津姫は、水の神、滝の神、祓(はらい)の神として、古来より人々の穢れを清め、厄災を祓う力を持つと信じられてきました。
しかし、その名前が記紀神話から消されたり、他の神様の影に隠されたりしてきた経緯は、今なお多くの歴史愛好家が謎として追っています。
「なぜ、その存在は隠されたのか?」
今回は、その謎解き旅の一環として、福岡県内で瀬織津姫が祀られているとされる神社をリスト化しました。
自分のメモ代わりでもありますが、よろしければご参考にどうぞ。
瀬織津姫が御祭神の神社リスト
*立川神社
参考書籍には「鳥取市福部町高江122」と記載。
そばに箭渓川が流れる。
*利川神社
参考書籍には「鳥取市青谷町早牛855」と記載。
そばに「日置川」が流れる。
近くに「早牛の金毘羅・太神宮灯籠」「妙台山 蓮華寺」「山根地区 荒神様の祠」あり。
GoogleMapの投稿画像で「春日灯篭」を確認。
これまで探してきたキーワード「金毘羅さま」「妙見信仰」「荒神様」「春日灯篭」「川(水)」と複数合致。
*櫻谷神社
〒680-0853 鳥取県鳥取市桜谷299
HP:https://tottori-jinjacho.jp/pages/166/
HPに「創立年代不詳。『稲場民談記』には荒神三社と記され、『因幡誌』には『鎮守大明神(祭荒神三社)摂社稲荷弁財天』とある。
明治元年(1868)櫻谷社、明治7年3月櫻谷神社と改称した。」と記載。
*水戸神社
〒680-0907 鳥取県鳥取市賀露町北1丁目21−8 賀露神社(かろじんじゃ)(境内社)
HP:http://karojinjya.jp/index.php
参考書籍には鳥取市賀露町1164」と記載。
海と「千代川」のそば。
鳥取県無形民俗文化財「ホーエンヤ祭」・西日本で唯一の神事「もみ火神事」。
GoogleMapの投稿画像で「春日灯篭」を確認。
*越路神社(こいじじんじゃ)
HP:https://tottori-jinjacho.jp/pages/151/
御祭神:須佐之男神 瀬織津比賣神
HPに「例祭には、子供榊が氏子内を廻る。秋祭に湯立神事を斎行。
雨乞踊り…中世の『風流(中世の芸能)』の趣をとどめている。干天慈雨を感謝し、花笠、たすき、胸かけ、手甲脚絆、白足袋姿、腰に締太鼓を付け両手にバチを持って太鼓を打ちながら踊る。
お滝子供相撲…8月25日。越路の奥地に祀る滝神に子供相撲を十二番奉納する。」 と興味深い記載。
GoogleMapの投稿画像で「春日灯籠」を確認。
*湯谷神社(合祀)
〒680-1231 鳥取県鳥取市河原町湯谷208
HP:https://tottori-jinjacho.jp/pages/870/
そばに「曳田川」が流れる。
GoogleMapの投稿画像で「春日灯篭」を確認。
*北村神社
HP:https://tottori-jinjacho.jp/pages/873/
そばに「曳田川」が流れる。
GoogleMapのクチコミに「御祭神 天照大御神、月読命、保食神、瀬織津姫命
このあたりの産土神として、日月大明神と称したと伝えられています。」と興味深い記述。
*東井神社(とういじんじゃ)
麒麟獅子頭(鳥取市保護文化財)。
そばに「千代川」が流れる。
*花原神社
HP:https://tottori-jinjacho.jp/pages/718/
HPに「創立年代不詳。往古より花原村の氏神で、近世まで妙見大明神(妙見社)と称した。
応永年中(1400頃) に虫害駆除のため素盞嗚尊を勧請したと伝える。享保12年(1727)と文化13年(1816)に社殿を改築した。明治元年に摂社瀧神(瀬織津姫尊)と八幡宮(応神天皇)を合祀して花原ノ社と称し、同6年に花原神社と改称した。大正元年に諸木神社(私都神社)に合祀したが、戦後、荒神社と共に分祀し奉遷した。」と興味深い記述。
*美幣奴神社(みてぐらじんじゃ)
HP:https://tottori-jinjacho.jp/pages/715/
HPに「創立年代不詳。『延喜式』神名帳(927)に「美幣沼神社」と記載されている。
近世まで忌部大明神と称した。私都郷の惣社。
明治元年に境内の稲荷神(保食神)と滝山の瀧神(瀬織津姫神)を合祀して、古称を重んじて改称した。
『因幡誌』に『社伝曰、祭神天太玉命と。按るに忌部は人の姓氏也、太玉命を以て祖神とす。美幣神と稱すること日本紀神代巻岩戸段に太玉命をして幣帛を作らしめ真榊木の枝に懸ること見ゆ。これその由縁なるべし』と見える。
また当社は始め字灰塚という所に鎮座していたが、後に現社地に遷座したと伝えられる。『みへぬじんじゃ』の別称も伝えられる。」と詳しい由緒が記載。
*八幡神社
HP:https://tottori-jinjacho.jp/pages/708/
そばに「私都川」が流れる。
HPに「創立年代不詳。かつて村内に産に悩む婦人が多かったので建保年中(1213~19)諾冉二神を紀州熊野より村内今熊に勧請して霊験を受けた。
天正9年(1581)兵火により焼失したため50mほど上方の現在地に移転して社殿を再建した。
近世まで十二社権現と称したが、明治元年に福地社と改め、同6年に福地神社と改称した。」と記載。
*隼神社
HP:https://tottori-jinjacho.jp/pages/647/
そばに「見槻川」が流れる。
*麻生神社
HP:https://tottori-jinjacho.jp/pages/709/
HPに「創立年代不詳。文治年中(1185~90)木曽義仲の残党が来住し、経津主命を奉祀したことに始まるとの伝承がある。」
*大野神社
〒680-0732 鳥取県八頭郡若桜町中原1211−1 池田神社(境内社)
HP:https://tottori-jinjacho.jp/pages/622/
HPに「大正4年12月大野の大野神社(もと龍王大明神 瀬織津姫命)、小船の小船神社(もと聖権現または聖大明神彦 火々出見尊 外四神)、落折の藤原神社(もと舟河原大明神 平経盛 天之御中主神)、中原カチ土居の加智神社(もと聖大明神 聖神)と中原滝ノ上の栃原神社(もとクレ谷大明神 大山祇命)の五神社を合祀し、当時の村名に因んで池田神社と改称した。
昭和20年10月合祀各神社を旧社地に分祀して境外末社としている。」
近くに「加地川」と「八大龍王権現大野神社」がある。
*䖝井神社(むしいじんじゃ)(参考書籍には「虫井神社」)
HP:https://tottori-jinjacho.jp/pages/583/
そばに「北股川」が流れる。
HPに「当社の東は古くより虫井谷と呼ばれている。『因幡誌』は、往古、夷住山に三神が降臨したという伝承があることと、『伊福部氏系図』の中に『武牟口命と云あり。景行天皇御宇、日本武尊に従て稲葉夷住山に住める荒海を征伐せらるる時に、荒海里人都都良麻参り迎へて槻の弓八枝献じける』という趣意の記述があることなどから、当社の創立を景行天皇の御代としている。山形郷十六村の総氏神である。中古以来数度の兵火にあい廃朽を余儀なくされた。
嘉慶元年(1387)の棟札には「奉造立普光山三社妙見荒海三瀧」等の文字が記されている。永享12年(1440)大江美濃介師真によって六~七町下の字ハセツコウに移転再興された。正徳4年(1714)に社殿を改築。『因幡誌』(1795)の神社絵図には三社造りの社殿が描かれている。文化4年(1807)に社殿を改築。明治初年の絵図には三殿並立の姿が描かれている。近世まで妙見社(葦津の妙見さん)と称したが、明治初年に旧号の虫井神社と改称した。
明治2年5月大呂村字サコ田に鎮座折井神社(もと折井大明神 天之御中主尊)(『因幡誌』は虫井神三社の母神としている)を合祀。明治4年に郷社に列せられた。大正5年6月、芦津の芦津神社(もと荒神 素盞嗚尊外二神)、八河谷の八河神社(もと三宝荒神 素盞嗚尊 宇賀魂命)、西野の西野神社(もと牛頭天王 素盞嗚尊)を合祀。大正10年10月社地を山麓の現在地に移し、本殿・幣殿・拝殿を新築した。」と記述。
「つき」「弓」「妙見」「瀧」「荒神」「素戔嗚尊」「牛頭天王」と、当サイトで追っているキーワードと複数合致。
*上市場神社(かみいちばじんじゃ)
HP:https://tottori-jinjacho.jp/pages/586/
HPに「創立年代は明らかではないが、口碑によると山城国祇園社(八坂神社)より勧請したと伝わり、牛頭天王と称した。明治初年に字瀧山鎮座瀧山大明神(瀬織津姫命)と境内鎮座稲荷大明神(宇賀魂命)を合祀し上市場神社と改称した。」
そばに「千代川」が流れる。
*諏訪神社(合祀)
HP:https://chizukankou-kurashiya.jp/event/spring/suwajinjya/
HPに「智頭町の諏訪神社は鎌倉時代(弘安元年・一二七八年)に信州の諏訪神社の分霊を移し祀った諏訪大明神がはじまりであり、以降、鎮火・戦の神様として崇められてきた。」
そばに「千代川」「興雲寺」。
GoogleMapの画像投稿で「春日灯篭」を確認。
*白坪神社
HP:https://tottori-jinjacho.jp/pages/601/
そばに「白坪川」が流れる。
HPに「創立年代不詳。近世まで太藝宮(たきのみや)又は瀧牛王と称した。明治5年白坪神社と改称する。天安2年(858)安藝国厳島大明神の分霊を勧請したとの口碑もあるが、往古より白坪川の渕瀬の神を奉斎したものである。『瀧ノゴオウ』『瀧ノボウサン』と呼ばれ、流行病の予防に効験あると伝わる。 」
当サイトで追っているキーワード「瀬織津稗」「たきのみや」と複数合致。
*風宮神社
HP:https://tottori-jinjacho.jp/pages/261/
HPに「創立年代不詳。
往古より瀬森大明神と称し、中野村の産土神である。
明治初年中野神社と改称する。大正5年2月、山長神社に合併されたが、戦後、旧社地に奉遷。」
そばに「北谷川」が流れる。
*中野神社
HP:https://tottori-jinjacho.jp/pages/261/
HPに「創立年代不詳。
往古より瀬森大明神と称し、中野村の産土神である。
明治初年中野神社と改称する。大正5年2月、山長神社に合併されたが、戦後、旧社地に奉遷。」
そばに「北谷川」が流れる。
*風宮神社
HP:https://tottori-jinjacho.jp/pages/242/
そばに「風宮神社の金毘羅灯籠」「横手の金毘羅灯籠」「志村川」あり。
*小鴨神社
HP:https://tottori-jinjacho.jp/pages/217/
そばに「大宮の金毘羅灯籠」「岩倉川」「大宮古墳」あり。
御祭神の一柱に「句々能智命」。
*大宮神社
HP:https://tottori-jinjacho.jp/pages/272/
そばに「三徳川」あり。
HPに「創立年代は明らかでない。
大瀬区の氏神で近世まで国主大明神(大國主命)と称したが、明治初年に大瀬神社と改称した。
大正10年4月に横手の氏神である横手字向谷の村社宮谷神社(もと三宝荒神 素盞嗚命)を合併し大宮神社と改称した。大瀬、横手の氏神である。」と記載。
*長田神社
HP:https://tottori-jinjacho.jp/pages/555/
そばに「法勝寺川」が流れる。
HPに「大正5年に法勝寺村馬場の大﨏神社(もと荒神 素盞嗚命)と稲荷神社(倉稲魂尊)、大國村與一谷の大林神社(もと荒神 須佐之男命)、鍋倉の鍋倉神社(もと荒神 須佐之男命)、西の前田神社(もと八幡宮 誉田別尊 足仲彦命 氣長足姫命 倉稲魂命 稚日女命 保食神)、絹屋の森脇神社(もと森脇大明神 句々廼智命)を合併し、同6年に法勝寺村法勝寺の机田神社(客大明神 句々廼智命)と杉﨏神社(もと伊勢宮 大日孁貴命 岩猛命)、武信の武信神社(もと客大明神 伊弉諾命)、徳長の熊野神社(もと熊野権現 伊弉諾命 伊弉冉命)、道河内の岩﨑神社(もと荒神 須佐之男命)、伐株の山口神社(もと山ノ神 大山祇命)、福頼の月村神社(もと月村大明神 月讀尊)を合併した。」と記載。
*江原神社
HP:https://tottori-jinjacho.jp/pages/564/
そばに「東長田川」が流れる。
磐座がある。
HPによると社紋は「右三つ巴紋」、「創立年月不詳。往古より旧東長田村江原の産土神で伊勢大明神と称していたが、明治初年に今の社号に改められた。神号額には『太神宮』と記してある。」と興味深い記載。
みやこ町の太祖神社の磐座に似た雰囲気。
*江原神社
〒689-4503 鳥取県日野郡日野町根雨631
HP:https://tottori-jinjacho.jp/pages/812/
HPには「日野郡日野町根雨697」と記載。
御神木と磐座がある神社。
HPに「創立年代不詳。往古、出雲國須賀の宮より勧請し、当社も須賀の宮と称して崇敬されたという。中古、あるいは中世に京都の祇園社(八坂神社)を勧請したものと思われ、近世は牛頭天王と称し、根雨、高尾、三谷、貝原の産土神である。」
GoogleMapの投稿画像で「春日灯篭」を確認。
瀬織津姫関連記事
【天照大神の荒魂・瀬織津姫】豊のくにあと記事一覧:すべての関連記事と連載記事↓↓
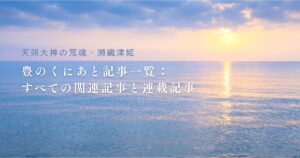
瀬織津姫と牛頭天王をつなぐ「滝ノ宮牛頭天王」が消された理由と二柱の関係とは?↓

歴史の謎をまとめて読みたい方はこちらから↓

参考書籍について
※書籍内の「瀬織津姫神全国祭祀社リスト」を参考にしておりますが、このリストは「神社本庁・各神社庁の資料、および各市町村史(誌)等を参考に、原則として『瀬織津姫』と祭神表示してまつっている神社に限定して掲載」しているそうです。(=天照大神荒魂・八十禍津日神・祓戸大神等の異称表記は除いておられる)
他のエリアの記事