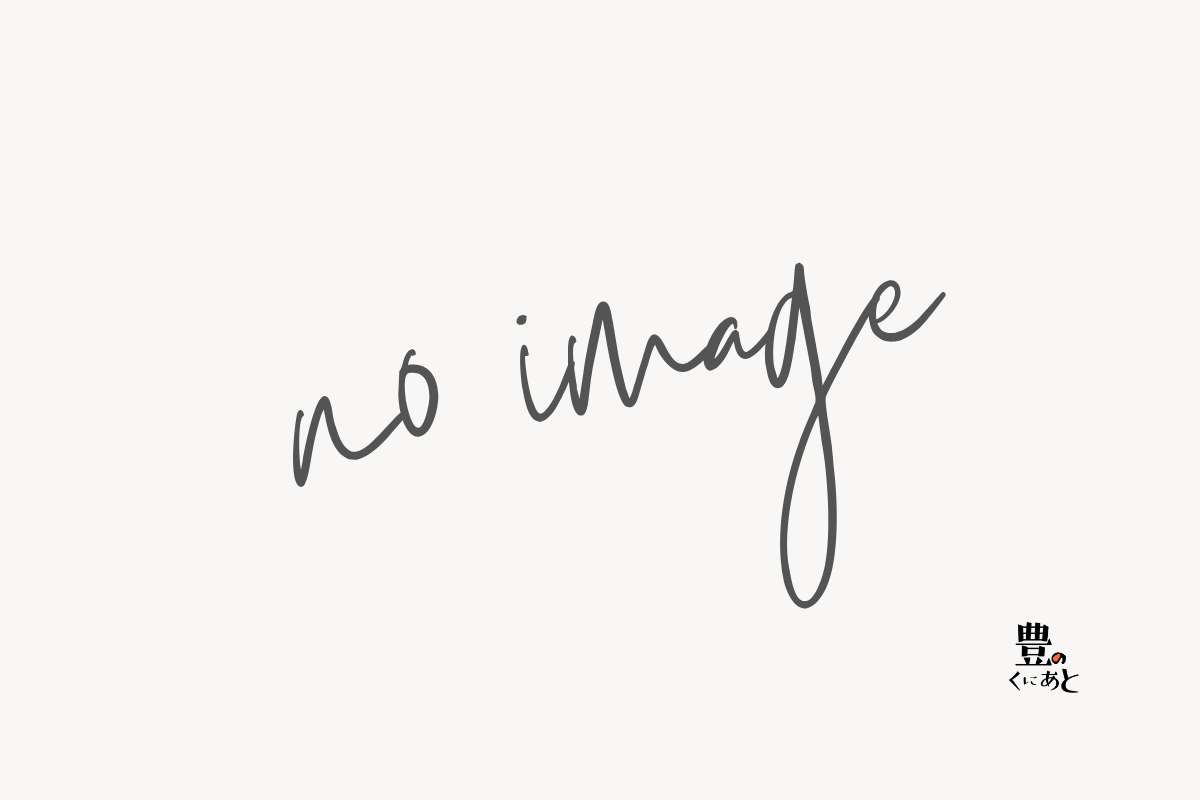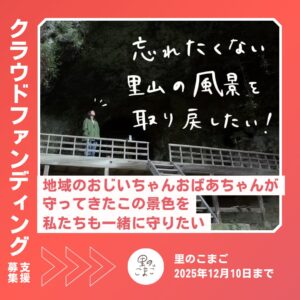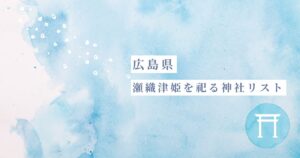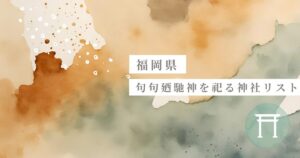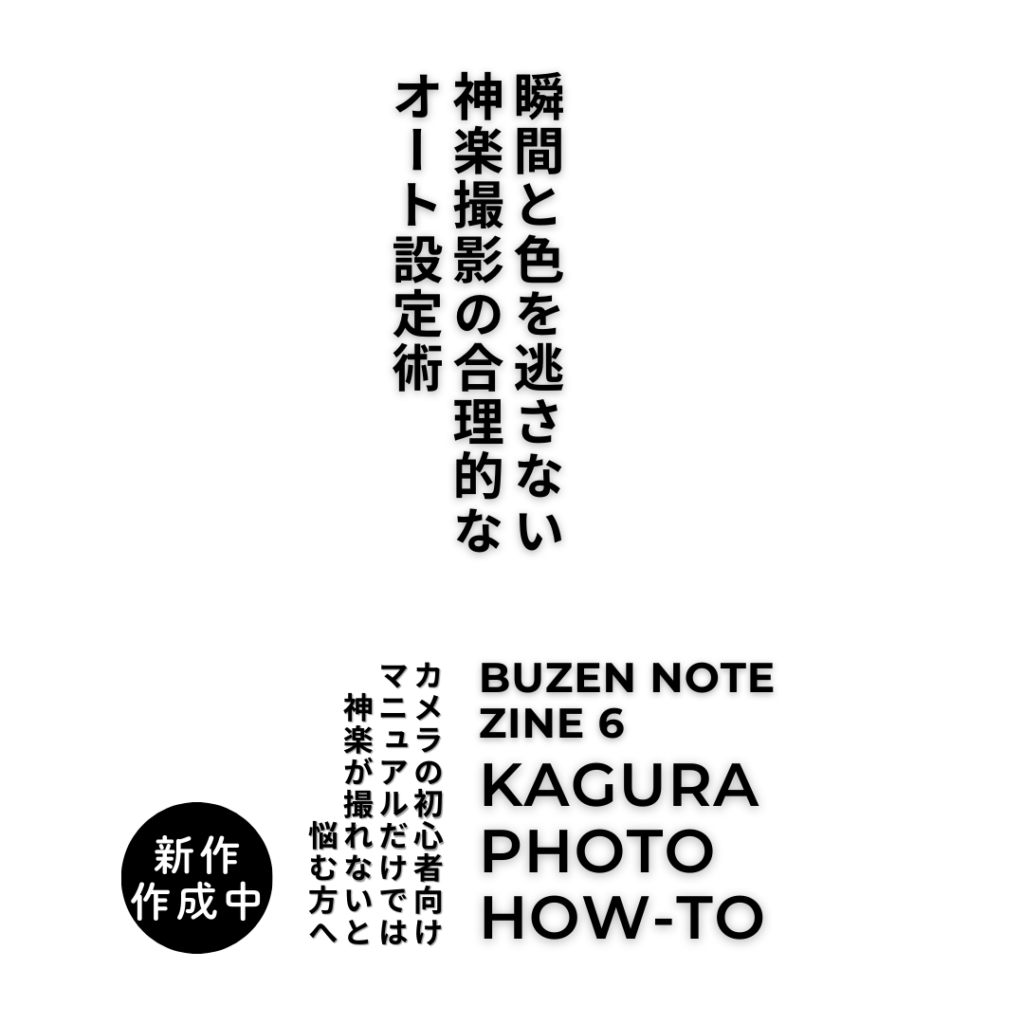史跡巡りをして、神社の由緒書きを見たり、地図を見ていくうちに、地名や神社名などが、現在のものと違うケースがあることに気付きました。
「乙比咩(おとひめ)」が「乙咩(おとめ)」に、「貴船神社」が元は「木舟神社」だったりと。
もしかしたら他にも違う字だったケースはあるかもしれないと、他のキーワードも注意して見るようになると、もしかしてこれもそうなのかと思う字がありました。
それは藤原氏に関する字です。
以前、中臣氏(後の藤原氏)のルーツが旧豊前エリアにあったかもしれないという推測記事を書いていましたが、その周辺の地名に「勝」という字が頻繁に見られたので気になっていました。
さらに、日本の象徴である富士山。
もしかしたら「藤山」だったのではないか?
字を巡る共通点が気になってしまいました。
単なる偶然の一致なのでしょうか?
あくまで今まで調べたことをつなげた時に浮かんだ素朴な疑問のようなもので、私の妄想ではありますが、書き出しておきたいと思います。
「木」が消される謎:記紀神話と古代信仰の狭間
「藤」について触れる前に、まずは「木」のキーワードについて、私の考えを述べます。
「木」の字が書き換えられた理由とは何か_
日本の神話には、イザナギとイザナミの子である「句句廼馳(くくのち)の神」という、明確な「木の神」が存在します。
しかし、他の主要な神々に比べると、その信仰が前面に出ることは少ない印象です。
これは一体なぜなのでしょうか。
もしかしたら、句句廼馳が象徴する「木」が、特定の土着信仰や、あるいはある渡来系の集団がもたらした技術や文化と強く結びついていたとしたら、その信仰は、中央集権的な神話体系を構築する過程で意図的に「薄められた」のかもしれません。
さらに、白山神社の御祭神である菊理媛(くくりひめ)神は、神話においてイザナギとイザナミの仲裁に入ったとされる謎多き神です。
その名が「括る(くくる)」に通じることから、物事を結びつける、あるいは「隠されたものを顕現させる」といった解釈も存在しますが、もう一つ意味があります。
新潟総鎮守 白山比咩神社の公式Webサイトに「くくりひめの『くく』とは木の祖神『句句廼馳の神』(くくのちのかみ)と申し上げて木がぐんぐん伸びていく様を。また、宇宙の大生命がぐんぐん伸び栄えてゆく生命の勢いを『くく』と表現し、『理』は『天の神を理といい、地の神を気という』と古書にあり、天の神様の事で、『媛』は女神、母性、万物を生み出すという意味であります。」と記載されています。
もし「木」が特定の信仰や氏族と深く結びついていたとして、その存在が消されることで、菊理媛が持つ「結び」の力が、本来結びついていたはずの何か、例えば「木」にまつわる信仰や、特定の渡来系氏族との関係を断ち切られ、あるいは曖昧にされていった可能性も考えられます。
これは、私が考えている「字が変えられる」理由の一つです。
海を渡った「木」の文化:徐福伝説と豊の国の繋がり
この「木」の謎を深掘りする鍵は、海を渡ってきた人々、すなわち渡来人にあると考えられます。
日本の神話に登場する「木の神」「緑化の神」とされる五十猛命(いたけるのみこと)は、紀伊国(現在の和歌山県)と深い関わりがあり、多くの樹木の種を運び、日本中に植えたと伝えられています。
これは広く知られた伝承ですが、ある大元出版の本では、出雲王国の伝承として、五十猛命が徐福の息子であるという説が唱えられています。
紀元前218年に大船団で日本へ渡来し、火明(ホアカリ)と称したとされる徐福。
もし彼らが高度な知識や技術を持っていたとすれば、彼らが持ち込んだのは、単なる移住だけでなく、「木」に関する高度な技術、例えば林業や建築、あるいは豊かな森を育む知識であったかもしれません。
さらに、その徐福の孫にあたる高倉下(タカクラジ)が、「秦国の梅の木をたくさん植えて『木之國』を作り、後の紀伊国となった」という伝承もあります。
これは、秦氏系の渡来人が、日本の国土形成、特に植樹や林業を通じて深く関わっていた可能性を示唆します。
彼らは、特定の「木」や「樹木」を神聖視していた、あるいは彼らの高度な技術そのものが「木」を象徴していたのかもしれません。
豊前の祭りに残る「木」の記憶:「紀」氏と水の神々
この「木」の系譜が、まさに私たちの住む豊前市にも残っているかもしれない、そう思わせる情報を見つけました。
豊前市の大きな祭礼行事「八屋祇園」です。
当社の春の大祭である神幸祭(じんこうさい)は八屋祇園(はちやぎおん)と呼ばれ、地元の方々に親しまれております。神社の縁起によると、第45代聖武天皇天平12年(740年)に「藤原広嗣の乱」が勃発し、当地の豪族であった紀宇麻呂(きのうまろ)公が平定の為に当社に戦勝祈願をして出兵いたしました。乱は無事に鎮圧され凱旋した紀宇麻呂公は御神威を尊び、当社に宮殿・神門を造営し、「八屋八尋濱(はちややひろがはま)」に神輿安置の仮殿(御旅所)を造り、神幸(お神様を御神輿に乗せてお運びすること)を行ったと記されています。
神幸行列は紀宇麻呂公の凱旋の様子を模しているとも伝わります。
大富神社ホームページから引用
八屋祇園の神幸祭の起源は古く、聖武天皇12年(740年)の藤原広嗣の乱鎮圧まで遡るといいます。
この乱の鎮圧に貢献したとされる郡主の一人に、上毛郡擬大領「紀宇麻呂(きの うまろ)」の名があります。
八屋祇園の行列は、この紀宇麻呂の凱旋の姿を模したものと伝えられているのです。
「紀」は「木の神」である句句廼馳の子孫とされる紀氏(紀伊国造)に繋がるかと思われました。
さらに驚くべきは、八屋祇園の一番最初の神事が、豊前市内の吉木(よしき)地区の「貴船神社」、次に「乙女八幡神社」で行われるという決まりがあることです。
- 「吉木」という地名にも「木」がつきます。
- 吉木の「貴船神社」は、水神・龍神を祀り、かつて「木舟神社」であった可能性。ここでも「木」と「水」「龍」のキーワードが見えてきます。
- 「乙女八幡神社」は、宇佐市の乙咩神社と同じ「おとめ」と読みます。宇佐の乙咩神社と同じく、「おとひめ」だった可能性があるかも?
- 地域の方によると「乙女八幡神社」は秋の神楽シーズンでも最初に舞が行われる格が高い神社であるとの情報
「藤」に隠された謎:富士山と権力の象徴
そして、この「木」と「水」の繋がりから、「富士山」についても同じように想像してしまったことがあります。
「乙比咩」が「乙咩」に、「貴船」が「木舟」であった可能性と同様に、「富士山」が実は「藤山」であったのではないかという妄想です。
富士山は、豊富な湧き水を持つことから、古くから水の神や龍神信仰と深く結びついてきたのではないかと考えました。
富士山近隣の富士宮市貴船町には「貴船神社」が存在します。
京都の貴船神社と同じく水神を祀る貴船神社が、富士山のすぐ近くにあったこと。
とても印象的でした。