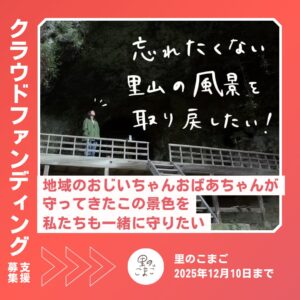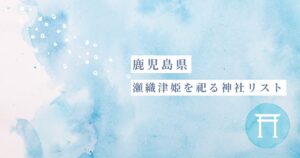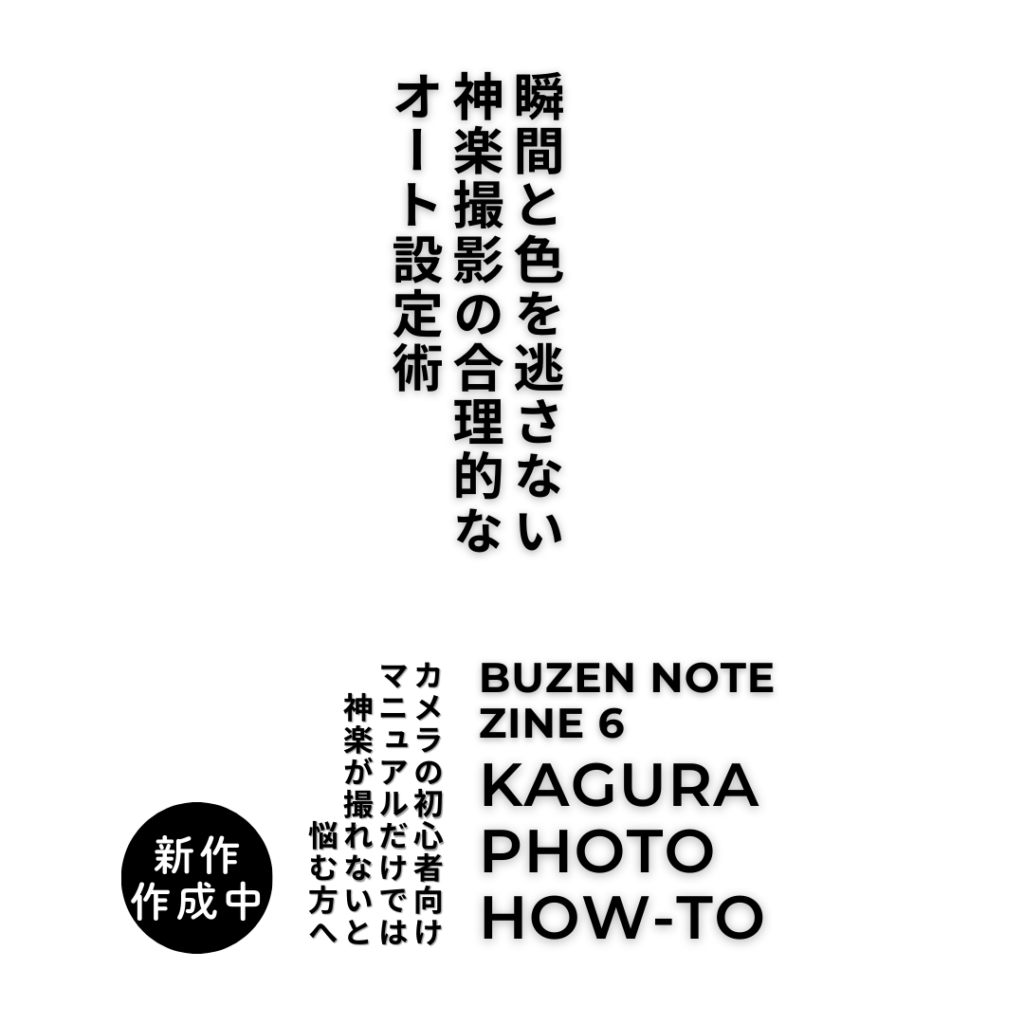日本の古代史の謎を追う本を読むと、記紀神話には深く語られない、あるいは意図的にその存在が曖昧にされた神々がいるのではないか、そんな説を目にするようになりました。
実際に自分の足で史跡を巡ってみると、特定のキーワードが気になるようになりました。
具体的には「水」「火」「木」「雲」「龍」そして「鹿」といったキーワードが、様々な地で意外な形で繋がりを見せているのです。
今回、それらのキーワードから、九州最大の神社である宇佐神宮について共通点をさぐってみたいと思います。
宇佐神宮の「原初信仰」に隠された一対の神

先日、この近辺の歴史に詳しい方から、驚く情報をいただきました。
宇佐神宮の元々の御祭神は、「男神と女神」だったという説があるそうです。
そして、その後に現在の八幡神へと変わっていったという伝承です。
残念ながら、ソースを忘れてしまったとのことでしたが、もしそれが事実であれば、これまで追いかけてきた謎のキーワードがまたつながる可能性がありました。
宇佐市や隣接する中津市には、なぜか貴船神社が多く点在しています。
貴船神社は水の神であり、多くは高龗神(たかおかみのかみ)と闇龗神(くらおかみのかみ)という一対の龍神を祀るとされます。
以前から、不思議なほどこのエリアの貴船神社が多いことが気になっていました。
もともと宇佐の地には、地主神として「一対の雌雄の龍神」が祀られており、それが貴船神(あるいは木舟神)と呼ばれていたのではないか、その可能性について考えてしまうようになりました。
現在の宇佐神宮の祭神が形成されていった経緯と照らし合わせると、驚くほど合致するのです。
- 地主神としての龍神(男神・女神)の存在。
- 大和朝廷との結びつきが強い新興勢力の大神氏や、辛島氏が、宇佐八幡神を創出。
- 宇佐八幡神が応神天皇と同一視され、神格が強化。
- さらに神の力を強化するため、神功皇后が加えられ、再び「一対(あるいは三柱)の神」としての形が整えられた。
この流れは、既存の地域に根差した信仰を完全に消し去るのではなく、新しい支配体制や思想体系の中に「取り込み」「再解釈し」「上位に位置づける」という、日本における信仰の再編や神仏習合の得意なメカニズムと一致します。
つまり、原初の「男神と女神」の要素が、形を変えて引き継がれた可能性が見えてくるのです。
国東半島・両子寺とみやこ町の「双子」の神々
この「一対の神」への信仰は、宇佐神宮周辺だけに留まりません。
北部九州の他の地域でも、その痕跡が見つかりました。

国東半島の中央に位置する両子寺(ふたごじ)です。
この寺の名前が示す通り、「ふたご」と、「男と女の双子」の権現像が祀られていることが分かりました。
実際に権現像の写真を見てみると、確かに男と女の組み合わせであることがはっきりと分かります。
寺の名前の由来である「ふたご」と、まさにリンクしているのです。
さらに、福岡県京都郡みやこ町犀川花熊にも、「二兒神社(ふがとじんじゃ)」という神社が存在します。
この神社も両子寺と同じく安産の神様として信仰されており、このエリアは、私が追っている古代の謎に関わる古墳が多く存在する地域です。
北部九州に根差す「一対の神」信仰の可能性
これらの点と点が繋がり始めると、北部九州エリアにおいて、以下のような信仰の系譜が浮かび上がってきます。
- 宇佐神宮の原初信仰における「男神と女神」。
- 貴船神(高龗神・闇龗神)に見られる「一対の龍神・水神」。
- 国東半島の両子寺や、みやこ町のふたご神社に見られる「男と女の双子」の神々。
- 金毘羅様や六所権現、牛頭天王と瀬織津姫の痕跡。
これらの要素はすべて、「一対の神」「双子」「水の力」「龍神」といった共通のテーマで結びつけられる可能性を秘めているのではないでしょうか。
かつてこの北部九州の地に、記紀神話とは異なる、「男と女、あるいは雌雄一対の龍神」を根源とする信仰が広く存在し、それが後の時代に形を変えたり、他の神々と習合したりしながらも、脈々と受け継がれてきたのかもしれない、そんな想像をしてしまうのです。
この記事を読んでいる方におすすめの記事
陰陽一対の御祭神の謎とは?↓

滝の神「瀬織津姫」と牛頭天王のつながりはなぜ消されたのか?↓
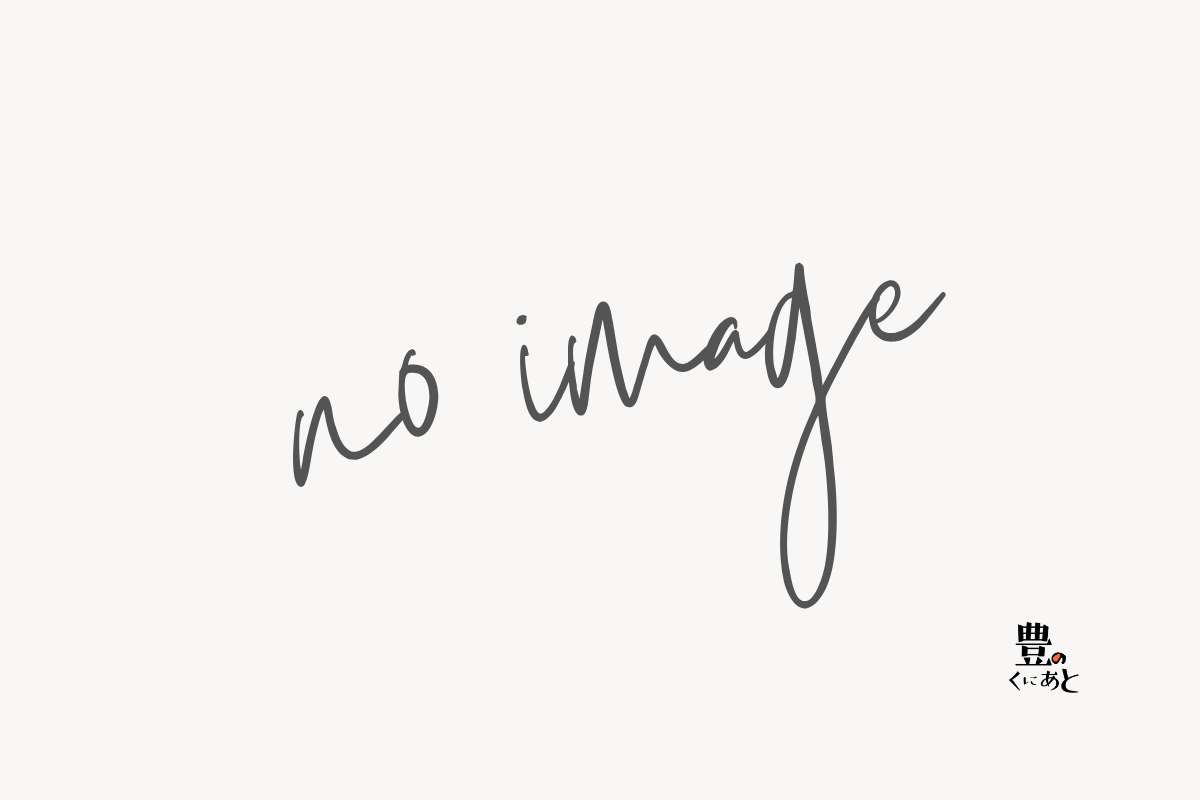
歴史の謎をまとめて読みたい方はこちらから↓