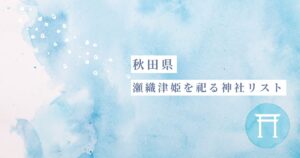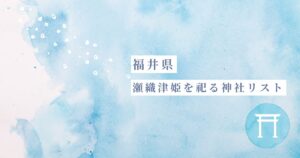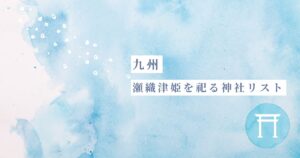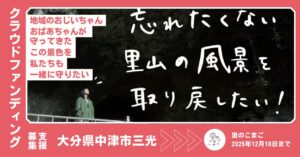福岡県内の古墳群近くの神社を訪れた際、境内で見つけた石灯籠に刻まれた「鹿」「雲」「月」の意匠が、強烈な印象を残しました。
この意匠は、奈良の春日大社に由来する「春日灯籠(かすがとうろう)」の特徴と酷似しています。
なぜ、春日神社ではないこの福岡の地方の神社に、奈良を象徴する灯籠があるのか。
現地の観察から浮かび上がってきた「春日」「藤原氏」「祓い」というキーワードを軸に、古代の記憶と地域信仰の深い繋がりを考察します。
神社に残された三つの痕跡
今回訪れた神社には、春日灯籠以外にも、古代信仰や歴史の繋がりを示唆する痕跡が残されていました。
拝殿の床下には、一対の鯱(しゃちほこ)と古い屋根瓦が置かれていました。
鯱は頭が龍や虎、体が魚の伝説上の生き物で、古くから火災除けや水難除けの意味で用いられてきました。
一対の龍を想起させる鯱の存在は、この地が龍神信仰と無縁ではなかった可能性を示唆しています。


最も注目したのが、「鹿・雲・月」の彫刻が施された六角形の石灯籠です。春日大社は、藤原氏の氏神を祀る総本社であり、この意匠は藤原氏の信仰を強く象徴するものです。

これらの痕跡が偶然ではないと仮定すると、この神社と藤原氏の信仰、そして地域信仰の重要な接点が見えてきます。
大祓詞(おおはらへのことば)の中で、四柱の祓戸の大神として一番最初に出てくるのが瀬織津姫です。大祓詞は、疫病が大流行したり、天変地異が起きた時、この祝詞をあげ祓い清め(浄化)させ、おさめようとするものであり、鎌倉時代から続いているようです。
風土記や偽書とされた『ホツマツタエ』等には載っていますが、正式な歴史の中には何一つ出て来ない謎多き女神 瀬織津姫。
瀬織津姫 – 草場一壽公式サイトから引用
瀬織津姫に闇龗神(くらおかみのかみ)であり龍神であるという説があること、そして春日大社においても、能の演目「春日龍神」があるほど龍神との縁が深いことは、「祓い」と「龍神」というテーマで、春日信仰と瀬織津姫信仰が重なり合っていた可能性を示唆しています。

鎌倉時代から豊前(ぶぜん)の地を治めた宇都宮氏は、藤原氏の流れを汲むとされています。
宇都宮氏に伝わる秘儀「艾蓬の射(がいほうのい)」が、邪気を祓い戦勝を祈願する術法であったという事実は、「祓」「春日」「藤原」というキーワードを強く結びつけます。
この地域を支配した藤原氏系の豪族が、氏神である春日信仰とともに「祓い」の力を重視していたと考えられます。
鶴姫の塚より蛇が這い出てきたという。
蛇の長さは五尺余り。つまり1.5mほどの長さだろう。かなり大きい蛇だ。
さらに、謎の蛇はとんでもない特徴を持っていた。
蛇だが、亀のような足がある。
蛇だが、牙がある。
蛇だが、ウサギのような耳がある。
蛇だが、ナマズのようなひげがある。
そして、両眼に金の斑点のようなものがある。
和樂web 美の国ニッポンをもっと知る!|侍女と共に磔にされた姫──宇都宮氏一族「もう1つの無念」を追い、福岡・宇賀貴船神社へから引用
この大蛇が祀られる宇賀貴舩宮が貴船神社系統であること、そして貴船神社が龗神(龍神)を祀っていることは、龍神・蛇神信仰が地域豪族の伝承に深く組み込まれていたことを示しています。
また、春日大社の主祭神である武甕槌命(たけみかづちのみこと)が雷の神であること、そして今回訪れた神社も雷に関係する神社であったという事実は、雷(空の力)と龍神(水の力)という古代からの自然神への信仰の連続性を示唆しています。
まとめ:重なるのは偶然か?それとも
この福岡の地方の神社で見られた「春日灯籠」は、単なる装飾ではなく、藤原氏の氏神信仰と、地域の豪族(宇都宮氏)の信仰、そして瀬織津姫や龍神といった「祓い」の神々の存在が複雑に重なり合う、古代の記憶を現代に伝える手がかりとなっているのでしょうか。
答えは得られませんが、可能性のひとつとして残しておきます。
この記事を読んでいる方におすすめの記事
石灯籠には意味がある?ある一対の石灯籠の謎↓

国東半島の山中に残る「海」の痕跡とは?↓

歴史の謎をまとめて読みたい方はこちらから↓