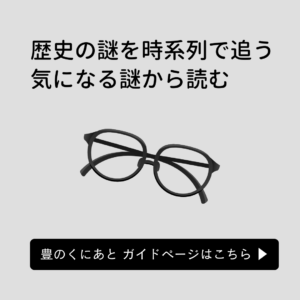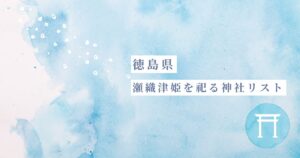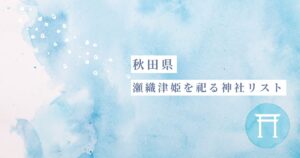豊前市に移住して以来、この地域の歴史や文化の奥深さに触れる日々を送っています。
最近、制作中の小冊子の掲載内容を確認するため、豊後高田市の文化財室の方とお話しする貴重な機会に恵まれました。その中で、以前から抱いていた素朴な疑問をぶつけてみたところ、思いがけない回答が返ってきたのです。
それが、今回のテーマである「金毘羅(こんぴら)様は海の神様ではなく、風の神様だった」という、固定観念を覆す事実です。
目次
私が文化財担当者の方に質問をしたのは、以前訪れた国東半島の山岳宗教「六郷満山」の聖地での疑問がきっかけでした。
六郷満山の本山の一つ、馬城山伝乗寺(まきざんでんじょうじ)の跡地(現在の真木大堂)背後の山頂近くには、ひっそりと金毘羅宮(こんぴらぐう)の石祠が佇んでいます。

山頂に海の神様が祀られているのはなぜか?という素朴な疑問に加え、その石祠が向く方角にある、存在感のある大きな山の名前がGoogleマップに載っていないことも気になっていました。

文化財室の担当者(Mさん)に尋ねたところ、「おそらく馬城山伝乗寺の本体はあの山、喜久山(きくやま)です。昔は花の『菊山』だったそうです」という情報と共に、次の驚きの事実を教えてくれました。
「風と雲の神様」としての金毘羅様
私が「山頂付近の金毘羅社は、海の神様ですよね?」と重ねて尋ねると、Mさんはこう答えてくれました。
「いえいえ、実は金毘羅様は、海の神様ではないんです。風の神様で」
豊後高田市の文化財室のMさんによると、金毘羅様は風の神様であり、海上の風はもちろん、山に吹きすさぶ風からも人々を守護してくれる存在として、海だけでなく山にも祀られているのだそうです。
「海の神様と思っている方が多いと思いますよ」というMさんの言葉通り、私のように金毘羅様を海の神様だと思い込んでいた方は、少なくないのではないでしょうか。
文献から裏付ける「天候を司る神」の側面
金毘羅様が「風の神様」であると知り、さらに調べていくと、四国新聞のサイトに、金毘羅様は風だけでなく「雲」の神様でもあるという、興味深い考察記事を見つけました。
塩飽や備中の海を航行する船からの目印として、高燈籠が建てられている。暗夜の嵐のなかでただ一点の燈は、迷走する船にとっては天の救けであった。また、その奥を見透かせば、うっすらと象頭山の威容が浮かんでいる。こんぴらさんは自然の猛威を司る風の神、雲の神である。祈りに応え、難破寸前の船に向かって、金の御幣が雲に乗って、飛んできて救けてくれる、劇的場面も数多く絵馬には描き残されている。
四国新聞「金比羅宮美の世界」- 「神聖な海域『塩飽の海』(作家・フランス文学者 栗田勇)」から引用
また、金刀比羅宮が鎮座する象頭山(ぞうずざん)について、以下のような説があります。
あわせて読みたい
山の中に残る「海」の痕跡――国東半島と宇佐の不思議
神社や仏閣を巡る中で、不思議なことに気がつきました。 それは、海から遠く離れた山の中に「海の痕跡」が残っていることです。 大分県豊後高田市 天念寺の伽藍を構成す…
国東半島に開かれた神仏習合の山岳宗教「六郷満山」の本山本寺8か寺の中でも最大規模を誇ったとされる「馬城山伝乗寺(まきざんでんじょうじ)」。その跡地(現在の真木大堂)の背後には馬城山がそびえ、約20分ほどで山頂の展望台まで登れます。
山頂近くに辿り着くと、ひっそりと佇む金毘羅宮(こんぴらぐう)の石祠が目に入ります。
その石祠が向かう方角には、現代の私たちが見ても「これはすごい」と驚くほどの存在感を放つ大きな山が見えるんです。