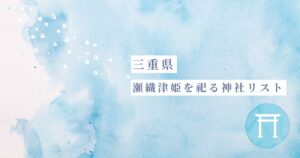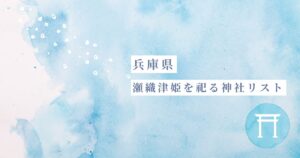国東半島の山深い地に位置する六郷満山の寺院、天念寺。ここでは毎年旧暦1月7日に、神仏習合の伝統を伝える勇壮な火祭り「修正鬼会(しゅじょうおにえ)」が行われます。
この天念寺の奥の院には、かつて**「六所権現」が祀られていた身濯(みそそぎ)神社があります。この山中の社に、なぜ海の波の紋様「青海波」**が描かれているのかという謎は、最近得られた一つの情報によって深まりました。
豊後高田市の学芸員の方から、「あそこに祀られているのは『八大龍王』です」という興味深い情報をいただきました。この龍神信仰の痕跡から、六郷満山における神仏習合の謎を考察します。

目次
八大龍王は仏教における水の守護神であり、降雨や水害除けの神格として、水神信仰の核をなす存在です。
火を多用する修正鬼会が行われる天念寺で、その鎮守として水の守護神である八大龍王が祀られていたことは、非常に重要な意味を持ちます。
火除けと治水
学芸員の方から「火除け」としての意味合いがあるのでは、という推測があったように、八大龍王は、修正鬼会の火に対する守護、そして寺院のすぐそばを流れる長岩屋川の治水を担う存在として位置づけられていたと推測されます。実際、天念寺境内には、暴れ川だった長岩屋川を鎮めるための川中不動も残されています。