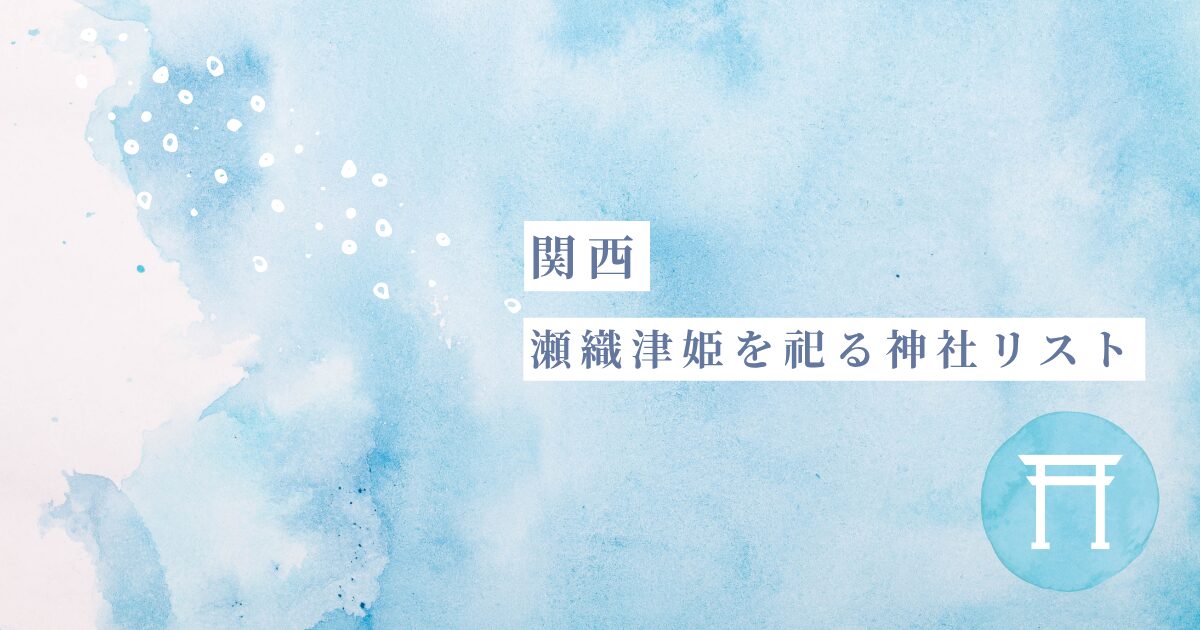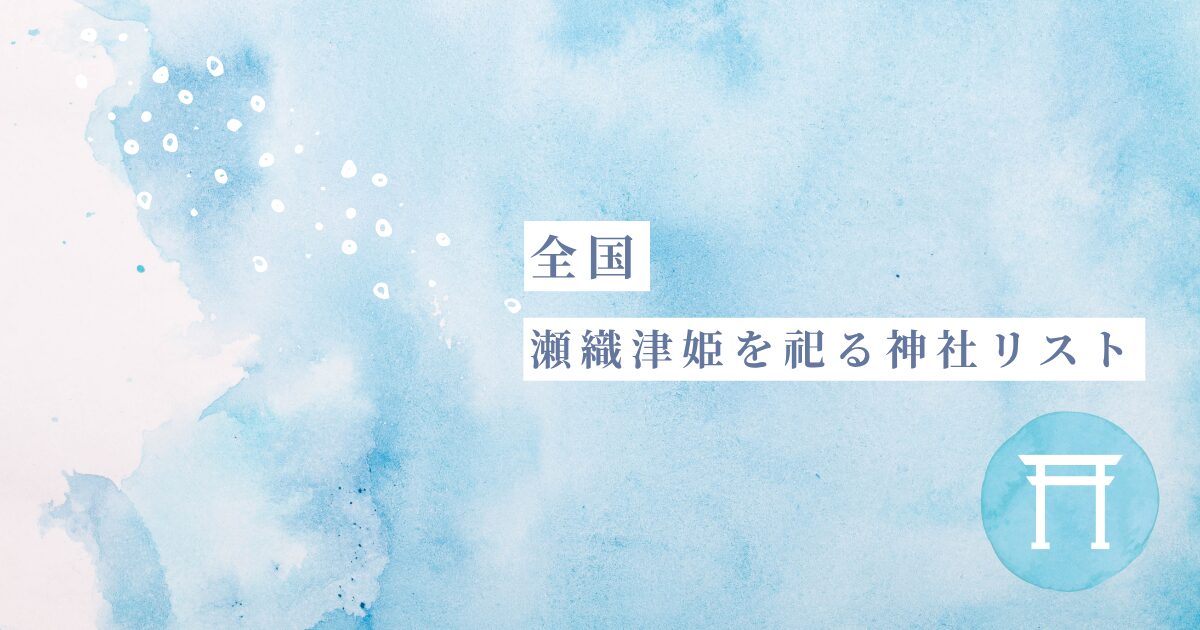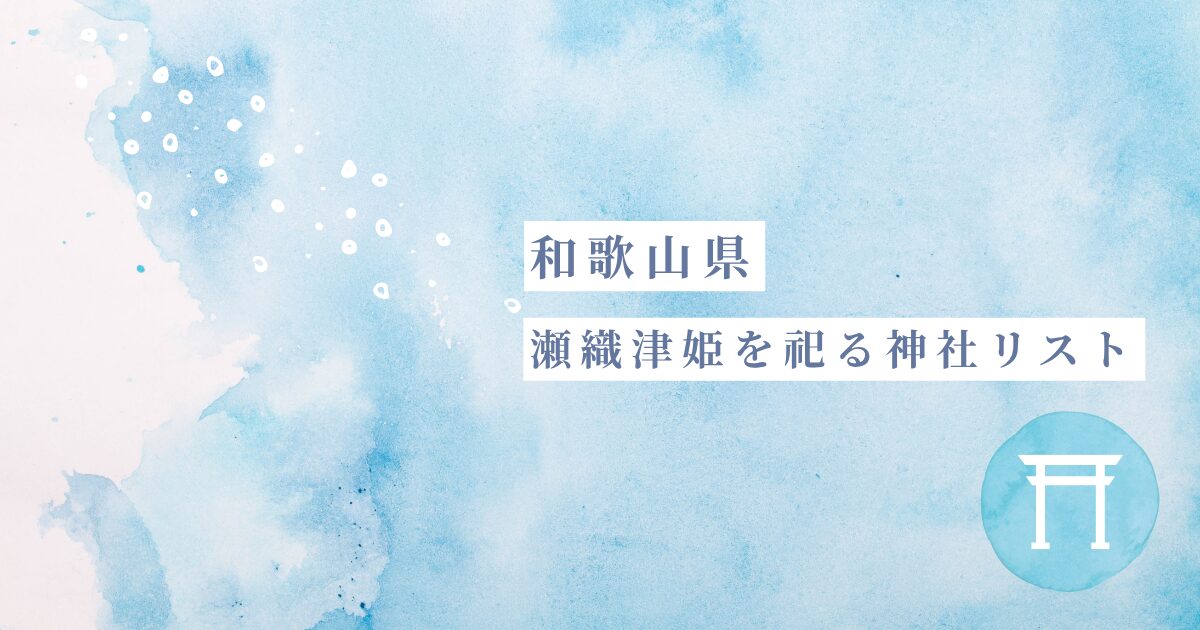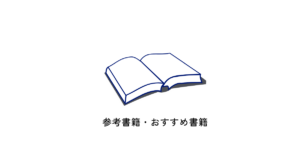古来より、日本各地には数多の神々が祀られてきました。
しかし、その中には、歴史の表舞台から姿を消し、ひっそりと隠された存在として語り継がれてきた神様もいます。その代表格こそが、瀬織津姫(せおりつひめ)。
瀬織津姫は、水の神、滝の神、祓(はらい)の神として、古来より人々の穢れを清め、厄災を祓う力を持つと信じられてきました。
しかし、その名前が記紀神話から消されたり、他の神様の影に隠されたりしてきた経緯は、今なお多くの歴史愛好家が謎として追っています。
「なぜ、その存在は隠されたのか?」
今回は、その謎解き旅の一環として、福岡県内で瀬織津姫が祀られているとされる神社をリスト化しました。
自分のメモ代わりでもありますが、よろしければご参考にどうぞ。
瀬織津姫が御祭神の神社リスト
*隅田八幡神社(すだたはちまんじんじゃ)
HP:https://sudahachimanjinjya.org/
そばに「須田八幡宮古墳」。
川に挟まれた場所。
*御祓殿
〒649-7205 和歌山県橋本市高野口町名倉1370番地 高野口八幡神社(境内社)
HP:https://wakayama-jinjacho.or.jp/jdb/sys/user/GetWjtTbl.php?JinjyaNo=4037
*山崎神社(合祀)
HP:https://www.wakayama-jinjacho.or.jp/jdb/sys/user/GetWjtTbl.php?JinjyaNo=3044
*祓戸神社
〒640-8139 和歌山県和歌山市片岡町2丁目9 刺田比古神社(岡の宮)(境内社)
GoogleMapの投稿画像で「春日灯篭」を確認。
*鹽竈神社(しおがまじんじゃ)
HP:https://tamatsushimajinja.jp/
GoogleMapの投稿画像で「春日灯篭」を確認。
HPに「鹽竃神社は、かつて「輿の窟」と呼ばれた岩穴に鎮座しています。
当社は元来、玉津島社の祓所であり、天野丹生明神(現在の丹生都比賣神社)の神輿が、玉津島社へ渡御される『浜降りの神事』(丹生都比賣神が玉津島稚日女神を表敬訪問される神事)の際に、先ずこの輿の窟へ渡らせられたと伝えられています。」と記載。
*稲荷神社
〒643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅1914 顕国神社(境内社)
HP:http://www.kenkoku.sakura.ne.jp/
GoogleMapのクチコミに「なぜ、房総半島に和歌山県と同じ地名が多いのか、その物的証拠となる一つがこの神社の手水桶です。こんな物が存在していたと知らず初めて参拝しましたので感動しました。
湯浅から魚を求めて房総に移住した方々が、故郷を思い寄進された手水桶とお聞きしました。醤油作りもここ湯浅から銚子に伝わりました。」と興味深い記載。
GoogleMapの投稿画像で「春日灯篭」を確認。
*寒川神社
「朔日川」そば。
木像女神坐像(平安後期)と木像武神坐像(鎌倉時代)が件文化財に指定されている。
*下阿田木神社
HP:https://www.facebook.com/nishinomiya.kawasuso
そばに「日高川」が流れる。
GoogleMapのクチコミに「伊弉諾命と伊弉冉命御祭神とする神社。他に火結神、速玉之男命、事代主命、櫛御氣野命で六柱祀られていた事から下愛徳六所権現と呼ばれる。922年に熊野から勧請されたのが始まりで遍座を繰り返し1109年に現在の場所に移る。」と興味深い記載。
*祓戸神社
〒645-0014 和歌山県日高郡みなべ町西岩代523 西岩代八幡神社(境内社)
HP:https://wakayama-jinjacho.or.jp/jdb/sys/user/GetWjtTbl.php?JinjyaNo=6038
HPに「岩代の地名は岩石信仰から名付けられたともいわれ、中皇命も「君が代も吾が世も知るや磐代の岡の草根をいざ結びてな」(『万葉集』巻一)と歌を詠まれている。」 と記載。
*荒島神社
HP:https://wakayama-jinjacho.or.jp/jdb/sys/user/GetWjtTbl.php?JinjyaNo=7064
HPに「古来より下山路村の氏神として奉祀するものが3社あった。
旧小家村には荒島神社、旧甲斐の川村には荒島神社、旧福井村には河内神社があった。
祭典は3社とも旧暦の6月19日を夏祭りとし、9月19日を秋祭りとして、この2期に行なわれていた。
その他、地神という甲斐の川字掛口に玉留神社、甲斐の川字方栗に八幡神社、福井字上平に金比羅神社、福井字坊垣内に嚴島神社、福井字中前に飛鳥神社があったが、定期の祭日としては、金比羅神社の旧暦10月10日以外は四季の祝日等をもって奉祀する例が多かった。明治6年に神社の改革があって、小家、甲斐の川の荒島神社を村社とし、他は全て無格社となる。」と興味深い記載あり。
*丹生神社(合祀)
HP:https://www.wakayama-jinjacho.or.jp/jdb/sys/user/GetWjtTbl.php?JinjyaNo=7065
HPに「当丹生神社の祭神は、丹生都比売と申し奉り、社地を巨勢原と称し、此の地に御鎮座せり。
大和国丹生川上神社の御祭神と御姉妹の神漏美なり。巨勢原は、大和朝廷の豪族巨勢一族が壬申の乱(672)に敗れ、この地に落ち延びて来た巨勢の地名であろう。」と興味深い記載あり。
*川上神社(河上大明神)
そばに「右会津川」が流れる。
見つからなかった神社
*祓之宮
東牟婁郡串本町
該当する神社が見当たらなかった。
それらしい情報としてこちらのWebサイトで「熊野古道・大辺路は古座川河口を渡舟でわたるルートであり、元禄年間に書かれた『紀南郷導記』には、『古座川ハ幅二町有り。船渡シ常ニ之レ有リ』と記されている。また、明治初期までは『祓川(はらいがわ)』とも呼ばれており、 『祓の宮』『という社殿のない神社があり、修験者などがここでお祓いをする習慣があったといわれている。」と興味深い記述を見つけた。
瀬織津姫関連記事
【天照大神の荒魂・瀬織津姫】豊のくにあと記事一覧:すべての関連記事と連載記事↓↓
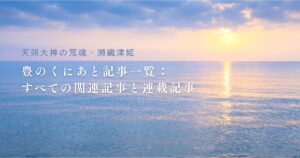
瀬織津姫と牛頭天王をつなぐ「滝ノ宮牛頭天王」が消された理由と二柱の関係とは?↓

歴史の謎をまとめて読みたい方はこちらから↓

参考書籍について
※書籍内の「瀬織津姫神全国祭祀社リスト」を参考にしておりますが、このリストは「神社本庁・各神社庁の資料、および各市町村史(誌)等を参考に、原則として『瀬織津姫』と祭神表示してまつっている神社に限定して掲載」しているそうです。(=天照大神荒魂・八十禍津日神・祓戸大神等の異称表記は除いておられる)
他のエリアの記事