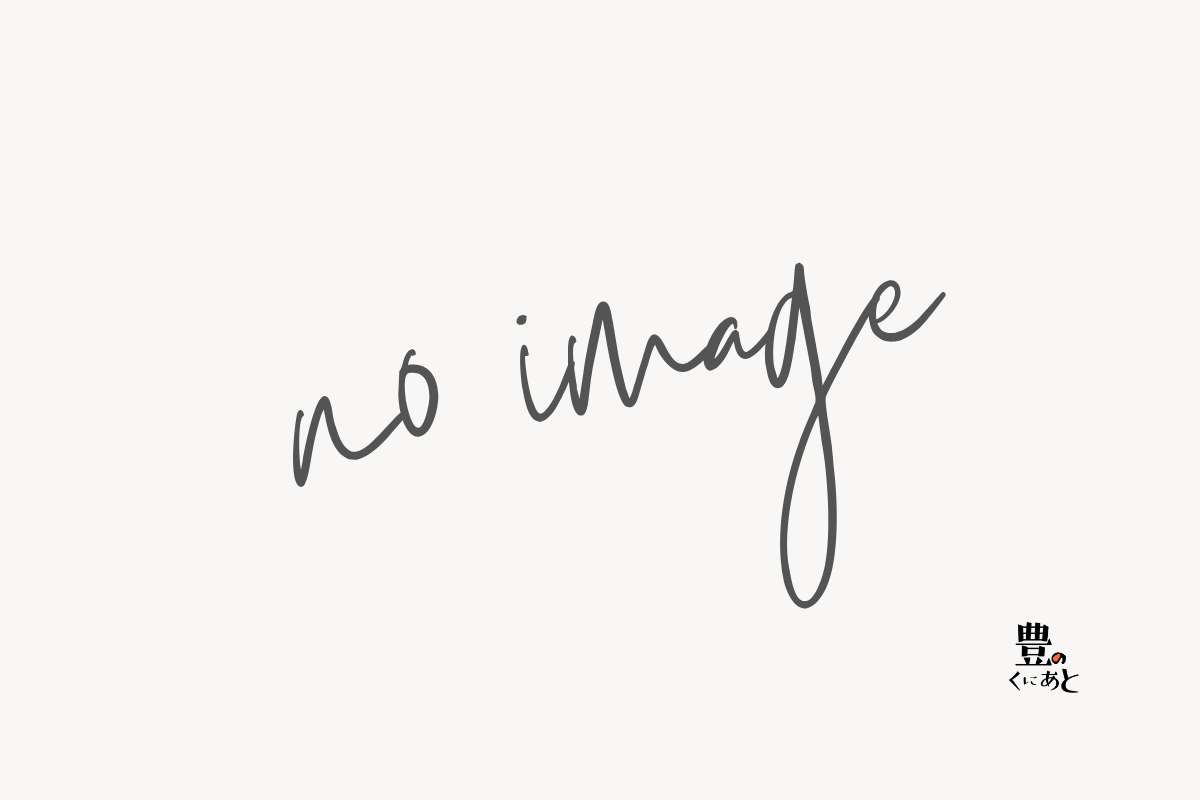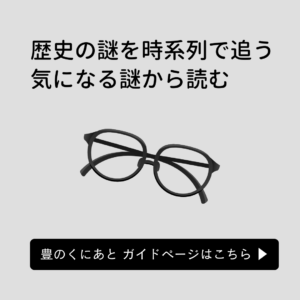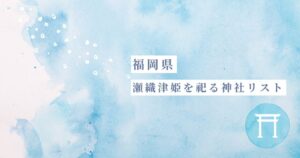日本の神話や信仰を深掘りする中で、歴史の表舞台から姿を消した謎多き女神、瀬織津姫(せおりつひめ)と、疫病鎮守の神である牛頭天王(ごずてんのう)の間に、機能的な関連があった可能性が浮かび上がってきました。
特に、豊前地域に残る神仏習合時代の社名に注目し、その隠された関係性を考察します。
瀬織津姫:水神と祓いの神の役割
瀬織津姫は、主要な歴史書である『古事記』や『日本書紀』にはほとんど登場しないにもかかわらず、各地で深く信仰されてきた女神です。
彼女は一般的に、滝の神、水神、そして罪穢れを祓い清める神として崇敬されてきました。
近年では、神仏習合下で不動明王と習合した例も見られ、その多岐にわたる正体から「歴史から意図的にその存在が消された女神ではないか」という説も唱えられています。
「瀧ノ宮牛頭天王」に残された水の痕跡

疫病を退散させる強力な神である牛頭天王は、日本ではやがて、荒ぶる神である素戔嗚尊(スサノオノミコト)と同一視されました。
この牛頭天王信仰の源流の一つは、京都の八坂神社の「元祇園」とされる播磨国・廣峯(ひろみね)神社です。
豊前地域、特に上毛町垂水(たるみ)にある八坂神社の前身は、かつて「瀧ノ宮牛頭天王(たきのみやごずてんのう)」と呼ばれていました。この社は、養老年間(717年~724年)に、疫病鎮守のため廣峯神社から勧請されたのが始まりと伝えられています。
この名称に注目すると、以下の重要な要素が結びついていることがわかります。
- 牛頭天王(素戔嗚尊): 疫病を鎮める荒ぶる神。
- 瀧ノ宮(滝の宮): 水神信仰の場所。
- 瀬織津姫: 滝の神・水神であり、穢れを祓い清める神。
この「瀧ノ宮牛頭天王」の名称は、牛頭天王という荒魂的な力(厄除け・疫病退散)が、水神(滝)の力によって補完され、瀬織津姫が担う「祓い清め」の機能と重なり合っていた可能性を示唆しているように思います。
つまり、牛頭天王と瀬織津姫は直接の夫婦神というより、疫病という「穢れ」を退散・祓い清めるという機能において、神仏習合下で祭祀的に一対の関係を持っていたと推測されます。

神仏分離が「繋がり」を断ち切ったか
上毛町の「瀧ノ宮牛頭天王」は、明治時代直前に発令された神仏分離令によって「八坂神社」へと改名されました。
この改名は、牛頭天王という仏教的要素の排除が主目的と思いますが、同時に「瀧ノ宮」という、地域の水神信仰の痕跡も公的な名称から消えることになりました。
この改名が、単なる神仏習合の解消だけでなく、牛頭天王信仰の背景に深く関わっていた水神・祓いの神との繋がりを、歴史から隠す結果となったと考えられます。
実際に、全国的にも「滝」や「貴船」といった水神に関わる名称が、神仏分離を機に変化した例は少なくありません。
この記事を読んでいる方におすすめの記事
瀬織津姫の関連記事・連載記事まとめ↓
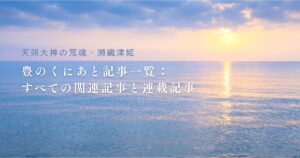
牛頭天王(スサノオ)の関連記事・連載記事まとめ↓
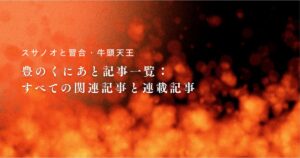
歴史の謎をまとめて読みたい方はこちらから↓