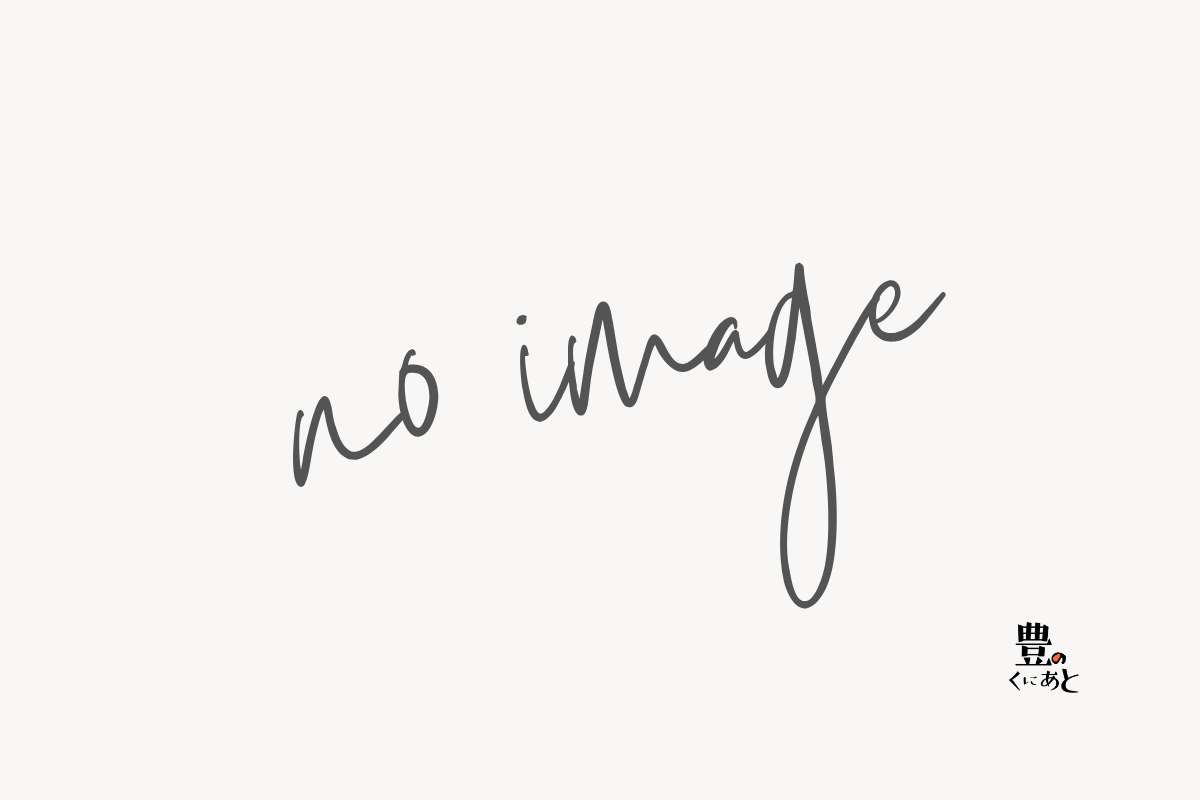須佐之男命と祓い清めの系譜、そして全国に広がる古代のつながり
今回取り上げるのは、全国の八百万の神々が集う地・出雲です。
ここには古くから「潮汲み」と呼ばれる風習が伝わっています。調べていくうちに、須佐之男命(スサノオ)や、祓い清めの信仰の流れに関わるさまざまな伝承が見えてきました。
あくまで個人的な視点ではありますが、現在わかっている情報をもとにまとめてみます。
出雲大社「潮の井」と須佐之男命の伝承の伝承
出雲地方の「潮汲み」は、神迎祭に先立ち 稲佐の浜で海水を汲み、禊として用いる重要な風習 とされています。
起源がいつかは不明ですが、地域に根づいた祓いの作法です。
体験記によると「潮汲み」の手順は以下のとおりです。
越峠荒神社から『神迎の道』を通って稲佐の浜へ向かい、海水(潮)を汲む。
その潮を笹に含ませながら、因佐神社 → 下の宮 → 上の宮 → 大歳神社 → 都の稲成 → 出雲大社と巡拝し、
家に持ち帰って玄関・神棚・仏壇・各部屋・家族を清める。
この風習に重なる形で、出雲市須佐町の 須佐神社の「塩の井」 という湧水の伝承があります。
地域案内「しまねまちナビ」によれば、
・塩の井の水はわずかに塩味がある
・潮の満ち引きで湧水量が変化する
・須佐之男命がこの井戸で潮を汲み、土地を清めたと伝わる
という特徴が記されています。
地質的に潮汐と湧水量が連動する現象は全国に例があるため、伝承と自然現象が重なった可能性も考えられます。
この伝承は、荒ぶる神として知られるスサノオが祓い清めにも関わる存在であったという神話のもう一面を示しています。
スサノオと薬師如来 ― 祓いと治癒の系譜
牛頭天王(スサノオと習合)と薬師如来が結びつくのは、江戸時代を中心に広がった寺社習合の信仰が背景とされています。
・牛頭天王=疫病退散の神
・その本地仏が薬師如来である(本地垂迹説による)
この関係性は確立した史実です。
熊野磨崖仏の大日如来像を薬師如来とする説は研究者でも見解が分かれていますが、「薬師信仰と祓い」が各地でセットになっていたのは確かです。
そう考えると、
・スサノオ
・牛頭天王
・薬師如来
・海水(潮)による祓い
は、地域差はあるものの、古くから「清め・治癒」を象徴する同じ信仰体系の一部として理解できそうです。
瀬織津姫(豊玉姫)との関連は神話体系によって異説が多いですが、「水の神」「祓いの神」としての共通性 は多くの研究者が指摘している部分です。
全国に広がる「潮汲み神事」
古代から続く浄化の共通モチーフ
出雲だけでなく、海水を汲んで祓いに用いる神事は全国に存在します。
九州・瀬戸内海沿岸:
>福岡市・筥崎宮「お潮井取り」
>行橋市・宇原神社の祇園行事
>大分県中津市「中津祇園・汐かき」
>豊後高田市・田染の潮汲み
>英彦山「御潮井採り」(行橋市の祓川との関係は伝承の範囲)
いずれも 海水=浄化の力 を象徴する儀式です。
関西・東海地方:
>大阪市・住吉大社
>伊勢神宮の白石持行事(海の石を清めに用いる)
関東にも類似の儀式が点在
これらの神事の共通点は、
>海(水)の浄化力
>穢れを祓い、清浄化する
>祭礼の前の「身と場の清め」
という、日本の古来の祓い文化そのものです。
この記事を読んでいる方におすすめの記事
瀬織津姫の関連記事・連載記事まとめ↓
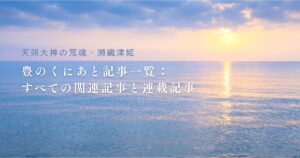
牛頭天王(スサノオ)の関連記事・連載記事まとめ↓
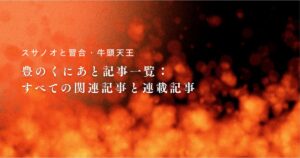
歴史の謎をまとめて読みたい方はこちらから↓