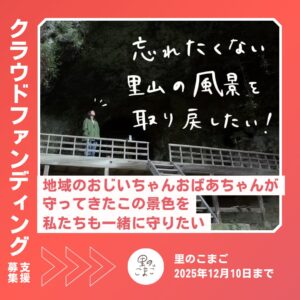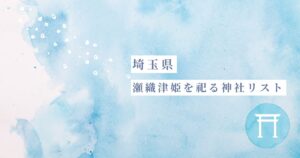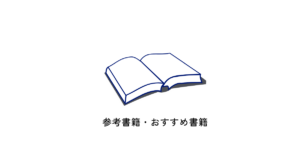三月下旬に、福岡県うきは市に一泊二日の旅をしてきました。
一日目は、うきは市浮羽町古川の素戔嗚神社に立ち寄り、二日目の午前中は、浮羽町西隈上の正八幡宮(隈上正八幡宮)へ。
あわせて読みたい
【うきは市浮羽町古川】素盞嗚神社に行ってきました(麺屋こばやし近く)
3月下旬の旅は福岡県うきは市 三月下旬に、福岡県うきは市に一泊二日の旅をしてきました。 うきは市は、北九州市から豊前市に移住する前に何度か行ったことがありまし…
あわせて読みたい
【うきは市浮羽町西隈上】狛鳥?狛鷽?が守る正八幡宮(隈上正八幡宮)に行ってきました
三月下旬に、福岡県うきは市に一泊二日の旅をしてきました。 一日目は、うきは市浮羽町古川の素戔嗚神社に立ち寄りました。 二日目の午前中は、浮羽町西隈上の正八幡宮…
正八幡宮の次に向かったのは、うきは市吉井町の若宮神社内「月岡古墳(つきのおかこふん)」「日岡古墳(ひのおかこふん)」です。
うきは市は古墳が多いエリアなのですが、そのなかでもなぜそこに行ったかといえば。