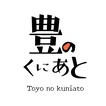日本の古代史、特に記紀神話の背後に隠された神々の足跡を追う「豊のくにあと」。
今回は、木の神とされる句句廼馳神(久久能智神)に焦点を当て、全国に点在するその神を祀る神社をGoogleMap中心に調べてみました。
(東北から北には、久久能智神がご祭祀の神社は見つけられませんでした。)
「消えつつある神」句句廼馳神の足跡
句句廼馳神は、日本神話においてイザナギとイザナミの子として生まれ、木の成長を司る神とされます。
しかし、その存在は他の主要な神々に比べて、現代ではあまり知られていません。
全国に点在するその名を持つ神社も、その数は限られています。
スサノオと藤原氏の影:春日灯籠が語るもの
句句廼馳神を祀る神社の中には、素盞嗚尊(スサノオノミコト)を合祀している例が複数見られました。
また、句句廼馳神を祀る多くの神社で「春日灯籠」、あるいはそれに類する石灯籠が見つかりました。
春日灯籠は、藤原氏の氏神である春日大社の象徴。
これが句句廼馳神を祀る神社に多く見られるということは、「木」と「鹿」、それに「藤原氏」というキーワードがつながります。
ただし、石灯籠が新しいか古いものかによって違いはあると思いますが。
「水」と「龍」との密接な繋がり
句句廼馳神は木の神であるにもかかわらず、その祭祀地や合祀神を調べると、驚くほど「水」や「龍」に関する要素が多く見つかりました。
- 海を見下ろす神社で、八大龍王と共に祀られる例(宮崎県の門川神社)。
- 罔象女神(みつはのめのかみ)や水波能売神といった水神が、句句廼馳神と共に合祀されている例(鳥取県の中村神社、京都府の大川神社、茨城県の蛟蝄神社など)。特に大川神社では、火・土・金・水と共に「五元神」として祀られ、古くから「祈雨の政」が行われてきたと伝えられます。
- 住所が「龍神」である和歌山県の丹生神社や、境内に「伊勢白竜大明神」の石碑があり、千年を超える大杉が白龍大明神として崇められる三重県の津田神社のように、「木」と「龍」と「水」の信仰が複合している事例。
- 茨城県の蛟蝄神社は、水の神である罔象女大神を祀り、社名が「伝説上の龍(蛟)」に由来するとされ、龍神の絵馬も存在します。
- 三重県の志等美神社では、句句廼馳神が「堤防の守護神」とされており、水害からの保護という側面で水との繋がりが見られます。
屋根瓦が語るメッセージ:鍾馗様と一対の鯱
特に印象的だったのは、愛媛県今治市の御崎神社で見つかった屋根瓦の装飾です。
社殿の屋根に鍾馗様と雌雄一対らしき、色と形が異なる鯱(しゃちほこ)が飾られていました。
- 鍾馗様は、疫病や邪気を祓うとされる中国由来の神様で、疫病退散の願いを象徴します。これは祇園祭の起源や、疫病除けの神としてのスサノオとの関連を彷彿とさせます。
関連記事を読む
「木の神」句句廼馳神とスサノオ、そして謎の渡来人徐福、空の神饒速日命がどのように繋がるのか。こちらの記事で詳しく考察しています。
句句廼馳神と同じ「くく」の名を持つ菊理媛、そして天照大神の「荒魂」とされる瀬織津姫、さらに牛頭天王といった「対なる神々」が、古代信仰の中でどのように織りなされてきたのか。その謎はこちらで深掘りします。
歴史の謎の記事をまとめて読むにはこちらから。
こんな記事もおすすめです
心と体がととのう鎮守の杜歩き。豊の国エリアには多くの鎮守の杜があります。
宇佐市安心院町の知る人ぞ知る、妻垣神社の広大な杜歩きはこちらから
写真愛好家であればはまり込む、神楽撮影。現・八坂神社(旧:滝ノ宮牛頭天王)での秋の唐原神楽の様子。
国東半島のパワースポット 長崎鼻内の行者洞窟へ。階段をくだるとそこは異空間でした。