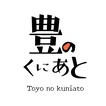大分県宇佐市も豊前市と同じく「海」と「山」両方ある市です。
そして広い印象があります。
山側の安心院エリアは盆地が広がっていて、初めて訪れた時は、子供の頃住んでいた大阪から奈良に行った時の感覚を微かに思い出しました。
奈良も盆地だったからかもしれません。

そんな安心院エリアには古い神社があります。
「三女神社」といって、市街地から安心院にやってくると通る、片側一車線でも交通量が結構ある道路沿いにひっそりと。
参道には、古墳時代末期の横穴古墳だという沢山の穴があるそうです。
そこ以外、神社の北側には弥生時代後期から古墳時代初期の宮ノ原遺跡が見つかっているそうですし、更に西側には同じく横穴式古墳である下市百穴、そして下市磨崖仏があります。

遺跡が集結するエリアにある「三女神社」。
どうも鳥居の扁額が妙でした。
「三女」の箇所が「二女」に見えました。
ちょうど立ち寄れた時にとりためていた写真をもう一度見返してもやはり「二女」です。
そしてよく見ると、鳥居本体と扁額を比べたら、扁額は新しいように見えます。
新しそうな扁額の字が、なぜ「二女」なのか分かりませんが、メモ代わりに残しておきます。
(写真は2023年10月4日撮影)

三女神社由来
鎮座地 宇佐郡安心院町大字下毛字三柱
一、祭神
田心姫命(たごりひめのみこと)・湍津姫命(たぎつひめのみこと)・市来島姫命(いちきしまひめのみこと)・他十柱神
一、由来
そもそも三柱山三女神は日本書紀神代巻に曰く
一、「即ち日神(天照大神)の生みませる三女神を以て葦原の中国(なかつくに)の宇佐島に降り居さし云々・・・」とあり、宇佐島とはこの地宇佐郡安心院邑、当三柱山一帯とされ、安心院盆地を一望する聖地で、宇佐都比古・ 宇佐都比売は三女神を祖神とするが故に全国唯一の 三女神の御名前を持つ社であるにして、水沼の君等がこれを祀る。爾来一貫してこの地に鎮座し今日に至ると伝えられる。
境内は古代祭祀の面影を漂わせ、幾多の史蹟と伝説とを有し、特に三柱石はじめ多くの陰石を有し、 宇佐神宮の元宮御許山(大元山)の御神体となり、 三個の女陰を形どる巨石の組み合わせと対照的に男根的存在を現しているところに神秘さを藏して いる。応仁天皇元年に社殿を改修したという記録が ある。
江戸時代に至り島原藩主累代これを崇敬し、三女神宮との異名を持ち、多くの末社を数え二十二ケ村の天神として崇敬せられると伝わる。 鳴呼霊妙にして霊験あらたか、子授け、安産、縁結び、開眼、病気平癒はじめ産業振興、家内安全、交通安全の大神とされる。 霊験あらたかにして里人はもとより関東・関西方面の崇敬者多く、当地方では宇佐神宮に続く多くの参詣者を記録し、隠れた神明の霊地としての存在大なるものがある。
参考リンク
下市百穴とは
6世紀末から7世紀に作られた横穴式古墳。下市磨崖仏に続く崖に32基ある。大正時代の道路造成の時、多くの古墳が堀り壊され、埋蔵品もその時散逸したが、一部の弥生土器、須恵器など家族旅行村の歴史民俗資料館に展示されている。
下市磨崖仏
下市百穴から続く崖に10体の諸仏が彫られている。半肉彫りという浅い彫り方から室町上期に作られたと想定されている。「安心院の七不思議」の一つであり、産後に乳の出が悪くて悩む母が不道明王にお粥を供えて、そのお下りをいただいたところ、乳が出るようになったので、「乳不動」「生不動」と呼ばれるようになった。
三女神社の情報
〒872-0521 大分県宇佐市安心院町下毛
歴史の謎の記事
宇佐神宮に八幡神が祀られる前の真の御祭神とは誰だったのか、豊玉姫との関連も考察しています。
宇佐神宮に隠された、原初の一対の「男神と女神」について考えてみました。
歴史の謎の記事をまとめて読むにはこちらから。
近くの史跡の記事
三女神社すぐ近くの「下市磨崖仏」の記事です。
宇佐市安心院町の知る人ぞ知る、妻垣神社の広大な杜歩きはこちらから