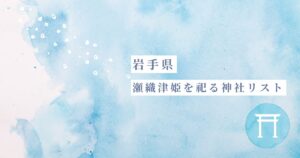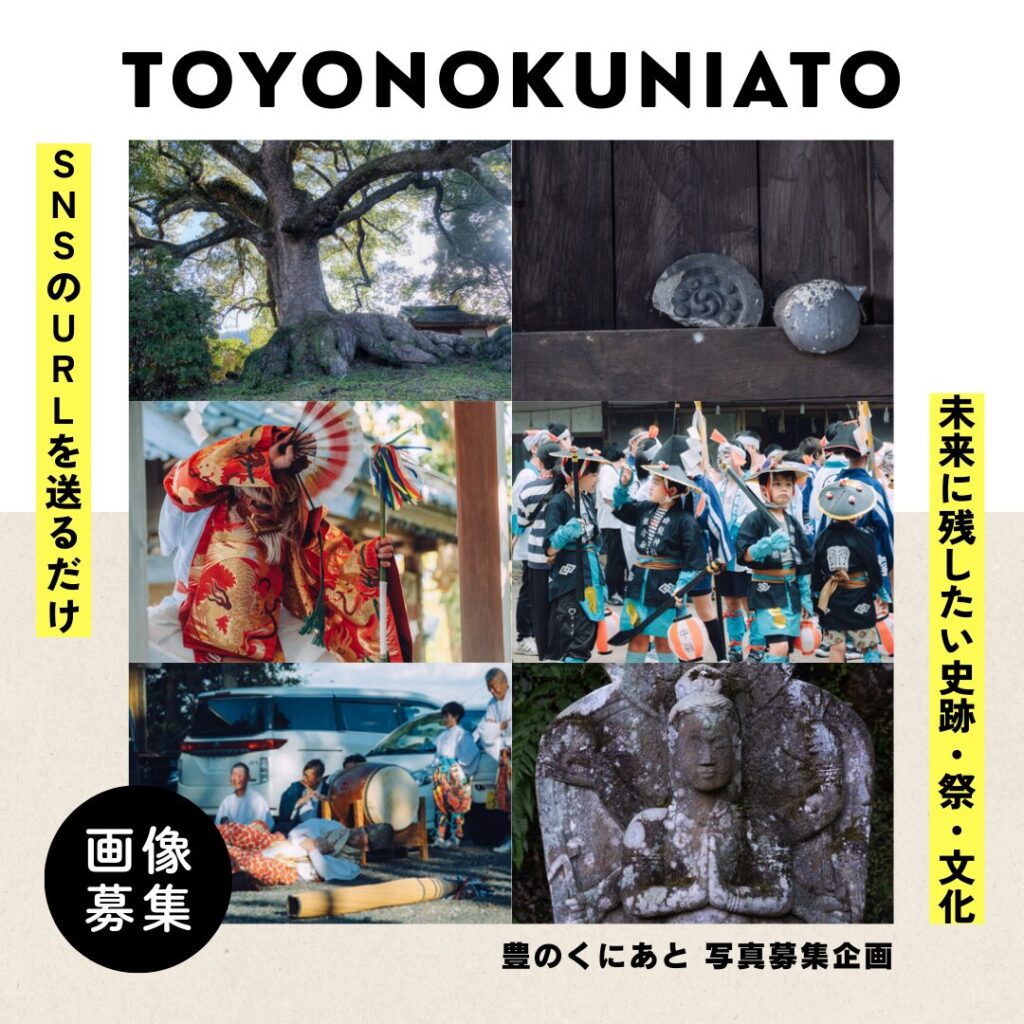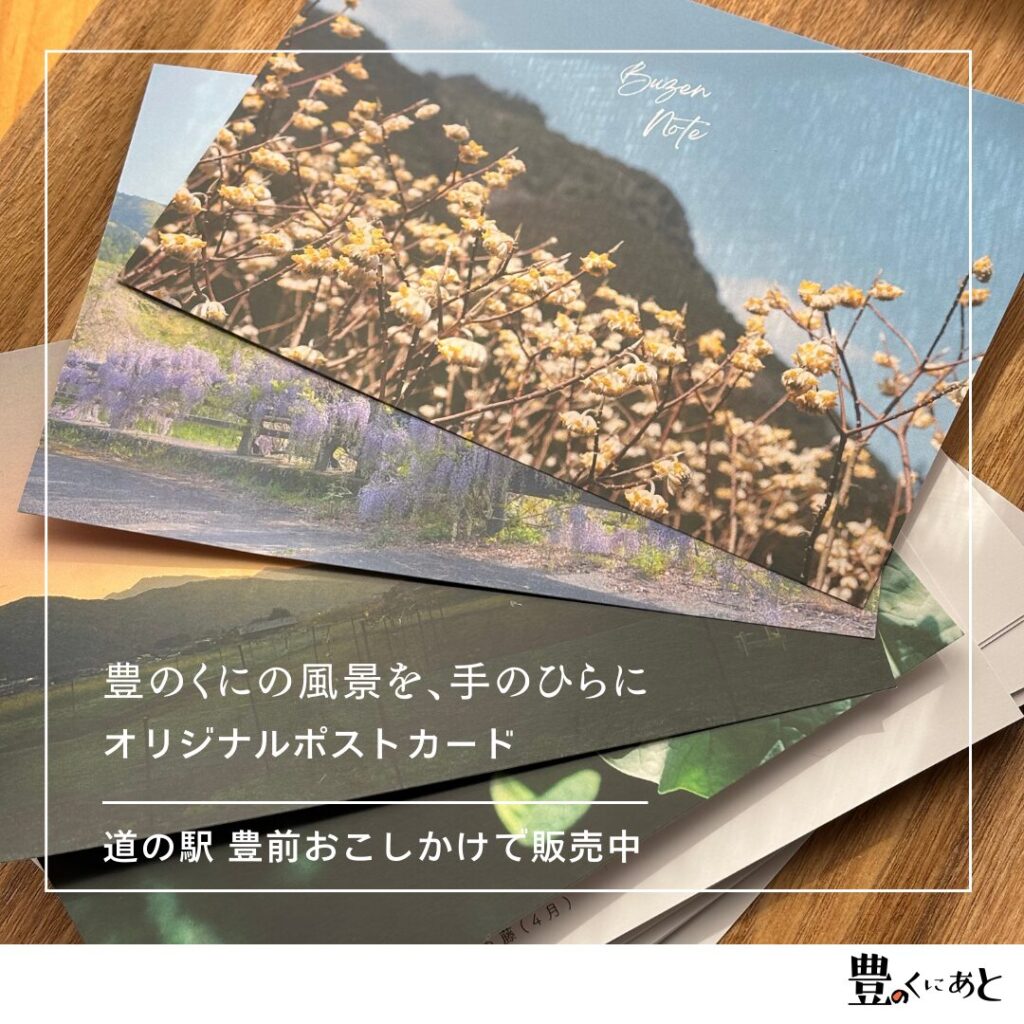宇佐市の乙咩(おとめ)神社で目にした「雷」の字が気になった。
あれは偶然だったのか、それとも何かの繋がりなのか。
答えを探すために、豊後高田市の「雷鬼の岩屋古墳」へ向かうことにした。
目次
宇佐市の乙咩神社に行った時のこと
豊のくにあと
【大分県宇佐市】古墳の上に鎮座する乙咩神社の謎:消された「乙比咩」と神々の系譜 | 豊のくにあと
豊前市へ移住してから、あることに気づきました。 それは、この地域に数多く残る史跡、特に古墳の上に神社が建っていることが多いことでした。 「古墳はお墓なのに、なぜ神…
「乙咩」という珍しい字が使われている神社の由来書には、かつてそこが「おとひめ神社」と呼ばれていたことが記されていた。
「おとひめ」から「おとめ」へ。
何があったのだろうか。
さらに気になったのは、御祭神に「雷」の名を持つ賀茂別雷命(かもわけいかづちのみこと)が祀られていること。
京都の賀茂神社ならともかく、宇佐の古い神社にこの神がいるのは違和感があった。
乙咩神社の古墳とも関係があるのだろうか。
「雷」といえば、宇佐神宮の三つ巴紋を思い出す。
巴は雷を象徴するとも言われている。
そして、自分が探している右三つ巴紋にも関わりがあるかもしれない。
豊のくにあと
行橋市内最大の前方後円墳「八雷古墳」と「八雷神社」へ | 豊のくにあと
2024年になってから「古墳」へ積極的に足を運ぶようになりました。 歴史好きなに、それまであまり行かなかった理由とは「お墓なので何か怖い」「無関係なので畏れ多い」 あ…
雷がつく神社や古墳はほかにもあった。行橋市には「八雷古墳」と「八雷神社」があり、特に八雷古墳は市内最大の前方後円墳でありながら、調査がほとんど進んでいない謎の古墳だった。
そして、豊後高田市にも「雷」がつく古墳があった。
それが「雷鬼の岩屋古墳」だ。
調べると、古墳の近くには「海神社」があった。
山の中にあるのに「海」の名を持つ神社。
豊のくにあと
【国東半島・豊後高田市】「天念寺」内の「身濯神社(六所権現)」で見つけた山の中の海「青海波」の意味とは…
豊前市に移住して以来、国東半島は頻繁に訪れる場所の一つです。昨年末、久しぶりに訪れた天念寺は、国東半島で平安時代に栄えた寺院群「六郷満山」を構成する寺院のひとつ…
これは、右三つ巴紋に関わる地ではよく見られる特徴だ。
雷と海。
その繋がりが気になり、現地へ向かった。
雷鬼の岩屋古墳レポ